化学情報, 薬学情報, データベースに関する文献
2005 年 (国内) (国外はこちら)
-1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, Latest
- 時実 象一, 「電子ジャーナルのオープンアクセスをめぐる議論と対立論文」,
情報社会試論,
2005, 10, 80-91.
(NIH, オープンアクセス推進者、出版社などの意見)
- 天野 絵里子, 原 健治, 石井 奈穂子. 「MyLibraryサービスの現状と可能性--京都大学・同志社大学・立命館大学の実例から」、大学図書館研究.
2005, (75), 1-12.
()
- 千原 秀昭, 「化学情報の今昔」, CICSJ
Bulletin, 2005, 23(3), 106-111.
(二次情報、化学情報協会、物質データベース)
- 藤原 鎮男, 「『情報化学』事始め」, CICSJ
Bulletin, 2005, 23(3), 112-113.
(情報化学と情報学)
- 國井 利泰, 「計算化学から情報科学、サイバー世界へ」, CICSJ
Bulletin, 2005, 23(3), 114-117.
(東京大学大型計算機センター)
- 山本 毅雄, 「わが国最初の文献・結晶構造データベースサービス TOOL-IR」,
CICSJ
Bulletin, 2005, 23(3), 118-120
- 前田 浩五郎, 「あしたの情報化学発展に向け只今の夜明け前に当り私からの御願い」,
CICSJ
Bulletin, 2005, 23(3), 121-123.
(質量スペクトルデータベース)
- 阿部 英次, 「コンピュータケミストリィ事始」, CICSJ
Bulletin, 2005, 23(3), 126-128.
(スペクトルから構造の解析)
- 田中 敏夫, 「新化学データベース、『PubChem』と『日化辞』」, オンライン検索,
2005, 26(4), 151-164.
(PubChem と日化辞 Web の収録データ、構造検索、法規制情報、ポリマー検索など)
- 山田 敦信, 「情報源ア・ラ・カ・ル・ト 第 9 回 特許情報を探す」,
専門図書館,
2005, (215), 40-41.
(特許電子図書館、知的所有権センター)
- 森田 歌子, 「ごぞんじですか? JDream II」, 専門図書館,
2005, (215), 48-55.
(JDream II の紹介)
- 藤田 節子, 「専門情報流通のための著作権 - 著作権委員会の活動」, 専門図書館,
2005, (213), 28-34.
(専門図書館における著作権の問題点について)
- 小林 晴子, 坪内 政義, 「電子ジャーナルへのアクセスルート: 愛知医科大学での調査」,
医学図書館,
2005, 52(4), 369-374.
(アクセスルートとして、PubMed、電子ジャーナルホームページ、OPAC, 検索エンジン、ScienceDirect
などのパッケージを比較)
- 松坂 敦子, 「『看護研究』誌の参考文献における雑誌評価の試み」, 医学図書館,
2005, 52(4), 375-381.
(雑誌毎の被引用数を調査)
- 増田 豊, 「COUNTER とは」, 医学図書館,
2005, 52(4), 399-400.
(COUNTER の解説)
- 南石 晃明, 「論文審査システムの開発」, 農業情報研究,
2005, 14(3), 159-170.
(農業情報学会が開発した論文審査支援システム rs.jsai
について)
- 佐藤 俊彦, 飯田 康人, 石田 裕美子, 今宿 芳郎, 小林 正樹, 関 奈緒子,
大門 良仁, 土居 美緒, 原 忠興, 村上 香子, 「特許に効く国内誌」,
情報管理,
2005, 48(9), 570-582.
(製剤・用途分野およびバイオ分野における特許反証資料として用いられた国内科学誌がどのデータベースに収録されていたか調査,
JSTPlus,JMEDPlus,医学中央雑誌が特に有用)
- 小野瀬 うた子, 「大学評価用データベース:
全学的データベースと部局 - 東北大学金属材料研究所の試み」, 情報管理,
2005, 48(9), 583-595.
(東北大学情報データベースの金属材料研究所での構築運用について)
- 兼子 利夫, 「世界各国の
IT 政策: 第 7 回 スウェーデン」, 情報管理,
2005, 48(9), 610-618.
(スウェーデン政府の主要な IT 政策)
- 名和 小太郎, 「録音録画補償金をめぐって
(下) - 概括的,統計的,匿名的」, 情報管理,
2005, 48(9), 622-623.
(著作権制度の原則の変遷, DRM)
- 時実 象一. 「e-サイエンスのための情報コモンズ構築に関する
CODATA 国際ワークショップ」. 情報管理.
2005, 48(9), 624-627.
(Science Commons、Creative Commons、NIH の公共アクセス方針、など)
- 江藤博文, 吉賀夏子, 只木進一, 「PHPによる論文投稿システムの開発」,
学術情報処理研究, 2005, (9), 113.
(学術大会の論文投稿のためのシステム)
- 安岡 孝一, 「Adobe-Japan1-6
と Unicode - 異体字処理と文字コードの現実」, 情報管理,
2005, 48(8), 487-495.
(Adobe-Japan1-6 は Unicode で区別できない異字体を区別できる)
- 阿蘓品 治夫, 「機関リポジトリを軌道に乗せるため為すべき仕事
- 千葉大学の初期経験を踏まえて」, 情報管理,
2005, 48(8), 496-508.
(千葉大学の機関リポジトリ(CURATOR)の構築経験)
- 後藤 敏行, 「電子ジャーナルのアーカイブ
- アクセスの観点からみた集中・分散の 2 方面戦略」, 情報管理,
2005, 48(8), 509-520.
(NESLi2, HINARI(The Health InterNetwork Access to Research Initiative),
LOCKSS)
- 兼子 利夫, 「世界各国の
IT 政策: 第 6 回 フランス」, 情報管理,
2005, 48(8), 539-546.
(RE/SO 2007, 電子商取引, P2AE)
- 名和 小太郎, 「録音録画補償金をめぐって
(上) - 私的使用の意味と価値」, 情報管理,
2005, 48(8), 549-550.
(西ドイツ音楽演奏件・機械的複製協会 (GEMA) とテープレコーダーメーカーとの紛争)
- 栗山 正光, 「学術情報リポジトリ」, 情報の科学と技術,
2005, 55(10), 413-420.
(機関リポジトリ,e-プリント・アーカイブ,電子ジャーナル,オーブン・アクセス運動,セルフ・アーカイビング,オープン・アクセス誌)
- 時実 象一, 「オープンアクセス運動の歴史と電子論文リポジトリ」,
情報の科学と技術,
2005. 10, 55(10), 421-427.
(最近の米国国立衛生研究所(NIH)の公共アクセス方針や欧州でのオープンアクセスの運動、分野別リポジトリ,研究機関リポジトリ,研究助成機関リポジトリ)
- 筑木 一郎,「英国における機関リポジトリの動向
- 電子学位論文プロジェクトを中心として」,
情報の科学と技術 , 2005, 55(10), 428-432.
(Theses Alive!,Electronic Theses,Daedalus)
- 行木 孝夫, 畠山 元彦,「プレプリントサーバの構築と運営」, 情報の科学と技術,
2005, 55(10), 434-438.
(北海道大学理学研究科数学専攻における GNU EPrints を利用したプレプリントサーバ)
- 郡司 久,「名古屋大学における学術機関リポジトリ 構築への取り組み」,
情報の科学と技術,
2005, 55(10), 439-446.
(名古屋大学における DSpace を使った「学術ナレッジ・ファクトリー」(AKF:Academic
Knowledge Factory))
- 川田力, 小川裕子, 南田泰子, 石田洋平, 下川公子, 石田由利子, 関口靖子,「ヨーロッパにおける医薬品の補足保護証明制度と保護期間の調査方法」,
情報の科学と技術,
2005, 55(10), 447-452.
(特許存続期間延長制度に相当するヨーロッパの医薬品の補足保護証明 (Supplementary
Protection Certificate; SPC) 制度と,その保護期間の調査方法)
- 浅見 文絵.「大学における剽窃行為とその対策
-英国・JISCPASを中心に-」. カレントアウェアネス. 2005.09.20, (285).
(英国における学生の剽窃の事例紹介)
- 竹内 比呂也. 「発展途上国における学術情報流通とオープンアクセス」.
カレントアウェアネス. 2005/9/20, (296), CA1566.
(HINARI, AGORA など)
- 文部科学省科学技術政策研究所. 「日本の科学技術の現状と今後の予測―我が国の研究活動のベンチマーキング」.
科学技術動向月報,
2005, (8).
(日本及び諸外国の研究活動の推移を、論文の量・質(引用回数)を国別、分野別に時系列で定量評価して分析。日本は質量とも材料科学、化学、物理分野でリードしており、環境生態学、数学、計算機科学、地球科学は低いままであった。海外の一流研究者が見た日本の研究活動は、材料系、環境系、情報通信系、ライフサイエンス系の順で評価が高い。)
- 李 相鎬, 金 惠善, 崔 善喜, 「韓国科学技術情報研究院での学術情報サービスの現況」,
情報管理,
2005, 48(7), 414-420.
(韓国科学技術情報研究院(KISTI) では学術情報データベースや電子ジャーナルの構築と提供をおこなっている)
- 兼子 利夫, 「世界各国の
IT 政策: 第 5 回 ドイツ」, 情報管理,
2005, 48(7), 451-461.
(ドイツ連邦政府の主要な IT 政策, 情報社会ドイツ 2006)
- 名和 小太郎, 「1978
年 7 月 10 日 - プログラムが著作物になった日 -」, 情報管理,
2005, 48(7), 465-466.
(1978 年に米国 CONTU 最終報告によって, プログラムが著作物になる道が開かれた,
このときのハーシー委員の反対意見)
- 佐々井 文吉, 「
戦略的研究開発支援システム -「パテントアトラス」の原理と活用法について」,
情報管理,
2005, 48(7), 467-470.
(概念検索を応用した類似特許の検索)
- 兼子 利夫, 「世界各国の
IT 政策: 第 4 回 英国」, 情報管理,
2005, 48(7), 382-389.
(UK online, e-Envoy, 電子政府局, Direct.gov)
名和 小太郎, 「単一世界システムの黄昏 - インテルサット小史」, 情報管理,
2005, 48(6), 393-394.
(インテルサットは米国主導で建設されたが, 米国が見捨てた結果破綻しかけている,
複合システムインターネットとの違い)
- 時実 象一, 「化学分野のデータベースの現状と動向」, 情報知識学会誌,
2005, 15(3), 36-41.
(化学構造、化学反応、物性・安全性情報などのデータベース)
- 国沢 隆, 岩田 修一, 「CODATA と Open Access」, 情報知識学会誌,
2005, 15(3), 42-47.
(遺伝子特許、データベースの権利、国連サミット WSIS、ベルリン宣言など)
- 長島 麻子, 「情報源ア・ラ・カ・ル・ト 第 8 回 海外統計の探し方」,
専門図書館,
2005, (214), 36-41.
(各国の統計機構・中央銀行、国際機関、地域経済圏、専門機関や業界団体、雑誌、民間の調査会社)
- 北條 充敏, 「岡山大学における学術情報基盤形成と Serial Solutions 社製品の活用」,
医学図書館,
2005, 52(3), 237-243.
(Access & Management Suite の使用経験)
- 久保 智靖, 「電子ジャーナル管理システム EBSCO A-to-Z」, 医学図書館,
2005, 52(3), 244-245.
(福井大学における使用経験)
- 田中 敦司, 「個人情報保護法と図書館」, 医学図書館,
2005, 52(3), 285-288.
(図書館の運営と個人情報保護について)
- NPO 法人日本医学図書館協会雑誌委員会, 「JMLA 電子ジャーナル・コンソーシアム・アンケート調査結果報告」,
医学図書館,
2005, 52(3), 270-280.
(JMLA 会員の状況、契約計画、要望など)
- 情報科学技術協会 OUG 特許分科会, 「医薬品の特許延長制度と延長情報の調査方法
(米国編)」, 情報の科学と技術,
2005, 55(9), 398-402.
(制度について, 調査方法, 調査の実例)
- 桑原 明子, 「情報源ア・ラ・カ・ル・ト 第 7 回 規格情報を探す」,
専門図書館,
2005, (212), 35-39.
(ISO, IEC, BS, DIN, JIS, ASTM など)
- 越久村 浩司, 「JAPIC の提供する医薬文献情報データベースについて (2)」,
薬学図書館,
2005, 50(3), 207-214.
(iyakuSearch のデータ項目の詳細)
- 松田 真美, 「『医中誌 Web』のご紹介 (2)」, 薬学図書館,
2005, 50(3), 215-222.
(データベース内容の詳細)
- 黒田 明子, 梶 正憲, 「JDream における JMEDPlus ファイルについて (2)」,
薬学図書館,
2005, 50(3), 223-229.
(日化辞 Web とのリンク)
- 棚橋 佳子, 「インパクトファクターの活用実態」, 薬学図書館,
2005, 50(3), 230-234.
(IF に関する論文の概観)
- 山本 和雄, 市古 みどり, 「国際図書館コンソーシアム連合 (ICOLC: International
Coalition of Library Consortia) 第 6 回欧州会合参加報告」、大学図書館研究,
2005, (74), 74-80.
(コンソーシアム運動の世界での広がり、ベンダーグリル: Elsevier, Blackwell,
Springer, OUP、利用統計、ゲーム理論)
- 樋口 重人, 「中国・韓国特許検索システム (CK-PRIME) の紹介」, 情報の科学と技術,
2005, 55(8), 335-338.
(機械翻訳を使って日本語で中国・韓国の特許を検索、日本語で閲覧可能)
- Zhang Yuehong (Helen); Qi Zhiying, 情報管理編集事務局翻訳, 「中国と外国の科学技術論文の生産から中国の科学技術定期刊行物の展望を予測する」,
情報管理,
2005, 48(5), 259-267.
(中国の科学技術論文は 1997-2002 年に年平均 19% の割合で成長)
- 兼子 利夫, 「世界各国の IT 政策: 第 3 回 カナダ」, 情報管理,
2005, 48(5), 283-291.
(歴史, カナダ産業省, CANARIE, SchoolNet, 電子商取引, マルチメディア)
- 陳 力, 「Google と図書館」, 情報管理,
2005, 48(5), 292-294.
(図書館員には Google を恐れているものもいるが, その機能は限られている)
- 名和 小太郎, 「科学者の法廷証言」, 情報管理,
2005, 48(5), 295-296.
(ベンディクティン副作用に関するダーバート訴訟における「科学的証言」について,
証拠とされた研究はピアレビューを経ていないので, 証拠要件を満たしていない)
- 木村 優, 「学術コミュニケーションの変革と大学図書館: 電子ジャーナル,
オープン・アクセス, 機関リポジトリ」, 医学図書館,
2005, 52(2), 129-137.
(電子ジャーナルと SPARC, オープンアクセスの動向, 機関リポジトリ)
- 岡田 英孝, 「電子ジャーナルにおける訂正記事の扱い」, 医学図書館,
2005, 52(2), 138-144.
(2003 年 PubMed 収載誌 114 タイトルから 901 件の訂正記事を調査)
- 末松 安晴, 「研究情報発信の社会的機能」, 情報管理,
2005, 48(4), 203-206.
(アーカイブの構築, 研究成果の発信, 学会の役割, SPARC/JAPAN, 連携)
- 園田 朗, 仲村 亮, 宮城 博, 設楽 文朗, 「国際海洋環境情報センター
(GODAC) における情報管理について」, 情報管理,
2005, 48(4), 214-219.
(深海調査記録映像, 刊行物, 観測データなど)
- 富川 弓子, 木村 美実子, 前田 知子, 「日化辞 Web 一般公開開始!」,
情報管理,
2005, 48(4), 220-225.
(日本化合物辞書を「日化辞 Web」として無料公開, ChemDraw のプラグインで構造検索も)
- 兼子 利夫, 「世界各国の IT 政策: 第 2 回 日本」, 情報管理,
2005, 48(4), 230-239.
(e-Japan 戦略, IT 予算, IT インフラ, ユビキタス・ネットワーク社会, 個人情報保護)
- 名和 小太郎, 「機微な, しかし秘密指定外の情報」, 情報管理,
2005, 48(4), 243-244.
(暗号分野の研究について)
- 衣笠 美穂, 「電子ジャーナルアクセス管理総合サービス『Serials Solutions
(シリアルズソルーションズ)』」, オンライン検索, 2005, 26(3), 77-86.
(Serials Solutions の紹介)
- 岡野 真一郎, 「EBSCO A-to-Z のご紹介」, オンライン検索, 2005, 26(3),
87-95.
(EBSCO A-to-Z の紹介)
- 細井 宏朗, 「スエッツワイズ・リンカー」, オンライン検索, 2005, 26(3),
96-105.
(SwetsWise Linker の紹介)
- 増田 豊, 「S.F.X の現状」, オンライン検索, 2005, 26(3), 106-117.
(S.F.X の紹介)
- 今井 康好, 「Web サービスとして進化する Dialog Link - 情報検索の変化の時代において」,
オンライン検索, 2005, 26(3), 118-130.
(Dialog Link の紹介)
- 古賀 美雪, 「Medical Subject Headings (MeSH) 2005 年版の変更点と最近の動向」,
オンライン検索, 2005, 26(3), 131-137.
(2005 年版は変更が少ない)
- Loria A, Arroyo P., 阿部信一抄訳, 「MEDLINE における使用言語と出版国の優位傾向とその要因」,
オンライン検索, 2005, 26(3), 138-139.
(英語文献の比率はほぼ 90%, アングロサクソン圏の出版比率は 68% でともに増加している)
- 古関 美津子, 「文献管理ツール RefWorks」, オンライン検索, 2005, 26(1/2),
17-23.
(RefWorks の利用経験)
- 和田 恭雄, 「海外雑誌に投稿するリスク」, 現代化学, 2005, (9), 30.
(海外雑誌に投稿すると研究を盗まれることがある)
- 時実 象一, 「台湾の科学技術情報利用」, 農学図書館協議会誌, 2005, (136),
1-8.
(台湾の研究機関, 情報センター, データベースの利用について)
- 越久村 浩司, 「JAPIC の提供する医薬文献情報データベースについて」,
薬学図書館,
2005, 50(2), 105-112.
(データベース内容, iyakuSearch, JIP, JOIS, 画面紹介)
- 松田 真美, 「『医中誌 Web』のご紹介」, 薬学図書館,
2005, 50(2), 113-120.
(データベース, 画面紹介)
- 黒田 明子, 「JDream における JMEDPlus ファイルについて」, 薬学図書館,
2005, 50(2), 121-128.
(概要, 物質索引, リンク, 収録対象誌)
- 永井 裕子, 「生物系電子ジャーナルパッケージ "UniBio Press"
をめぐって - 学術情報流通の中での障壁とは何か?」, 薬学図書館,
2005, 50(2), 128-133.
(UniBio Press 設立の理由, 今後の方向など)
- 松下 茂, 「著作権法改正と図書館/利用者の視点から」, 薬学図書館,
2005, 50(2), 134-138.
(第 6 回図書館総合展フォーラムのまとめ)
- 植村 八潮, 「図書の電子化と可能性」, 薬学図書館,
2005, 50(2), 141-146.
(事典・辞書, 学術電子図書, 読み物, e ラーニング)
- 棚橋 佳子, 「インパクトファクター - 本来どう見るべき数字で, どう使うと有効か?」,
薬学図書館,
2005, 50(2), 147-151.
(JCR, 数字の読み方, 計算, 原著論文誌, 論文)
- 呑海 沙織, 「中国における学術図書館コンソーシアムと電子図書館プロジェクト:
CALIS, CADAL から CADLIS へ」, 農学図書館協議会誌, 2005, (136), 9-13.
(CALIS の歴史と CADLIS について)
- 尾身 朝子, 時実 象一, 山崎 匠, 「研究助成機関とオープンアクセス
- NIH パブリックアクセスポリシーに関して」、情報管理、2005,
48(3), 133-143.
(NIH は 2005. 5. 2 より、助成研究成果の論文を PubMed Central に提出するよう研究者に要請することになった、その経緯と反響について)
- 久保田 壮一, 植松 利晃, 山崎 匠, 近藤 裕治, 時実 象一, 尾身 朝子,
「JST リンクセンターを利用した電子ジャーナルのリンクの現状」, 情報管理,
2005, 48(3), 149-155.
(JST リンクセンターは J-STAGE の電子ジャーナル, JST のデータベース・サービス,
外部のデータベースと電子ジャーナルをリンクする)
- 土屋 利雄, 岩瀬 良一, 齋藤 秀亮, 「独立行政法人海洋研究機構 (JAMSTEC)
における観測データの管理と公開」, 情報管理,
2005, 48(3), 163-170.
(船舶, 潜水調査線, 調査観測機器による観測データのインターネット公開)
- 兼子 利夫, 「世界各国の IT 政策: 第 1 回 米国」, 情報管理,
2005, 48(3), 176-184.
(クリントン政権からブッシュ政権にまでの情報技術政策, ネットワーク情報技術研究開発プログラム)
- 名和 小太郎, 「私的空間の範囲 - 個人情報の保護をめぐって」, 情報管理,
2005, 48(3), 188-189.
(電話の盗聴, 航空写真, 赤外線カメラ)
- 加藤 信哉, 「電子ジャーナルの現状」, 情報の科学と技術,
2005, 55(6), 242-247.
(電子ジャーナルのタイトル数, 利用状況)
- マーティン・リチャードソン, 的場 美希訳, 「オープンアクセス: 大学出版局の見解」,
情報の科学と技術,
2005, 55(6), 248-250.
(Oxford University Press の見解)
- 高橋 昭治, 「エルゼビアの電子出版戦略」, 情報の科学と技術,
2005, 55(6), 251-256.
(サイエンス・ダイレクトの現状, オープンアクセスに対する見解, など)
- 田邊 稔, 山田 雅子, 「慶應義塾大学における電子ジャーナル管理の現状と展望
- EJ アクセシビリティを中心として」, 情報の科学と技術,
2005, 55(6), 257-264.
(慶応義塾大学メディアセンターの経験)
- 渡邊 由紀子, 「電子ジャーナルの導入とその影響について - 九州大学の事例」,
情報の科学と技術,
2005, 55(6), 265-270.
(導入の経緯, 利用支援, 利用動向)
- 清水 美都子, 「公共の特許情報検索サービスの現状と課題」, 情報管理,
2005, 48(2), 63-716.
(USPTO Patent Serach, esp@cenet, WO IPDL, DEPATISnet, 特許電子図書館, Seaching
KPA, SIPO Patent Search, 台湾 Domestic Search)
- 服部 博之, 秦 利男, 「企業図書館における文献複写業務の実際: (株)
日立製作所日立研究所の事例」, 情報管理,
2005, 48(2), 72-77.
(著作権集中処理機構などとの契約状況, 運用状況, 文献入手依頼システム)
- 林 和弘, 太田 暉人, 小川 桂一郎, 「日本の電子ジャーナル事業の課題と展望:
日本化学会での取り組み」, 情報管理,
2005, 48(2), 87-94.
(独自電子化時代, J-STAGE, 有料化など)
- 国立情報学研究所 国際学術情報流通基盤整備事業推進室, 「SPARC/JAPAN
にみる学術コミュニケーションの現状と課題」, 情報管理,
2005, 48(2), 95-101.
(事業の成果と平成 17 年度の活動)
- 名和 小太郎, 「実現性 99% 以上」, 情報管理,
2005, 48(2), 113-114.
(「IPPC 地球温暖化第 3 次評価報告書」における信頼度の定義)
- 安岡 孝一, 「QWERTY 配列再考」, 情報管理,
2005, 48(2), 115-118.
(名和小太郎氏の記事の再考)
- 川崎 道雄, 「中国最大の論文データベース "CNKI" とその新しい商品「CNKI
カード」の紹介」, 情報管理,
2005, 48(2), 119-123.
(CNKI の紹介と CNKI カードによる利用)
- 宮入 暢子. 「オープンアクセスのインパクト分析」.
カレントアウェアネス. 2005/6/20, (284), CA1559.
(オープンアクセスによって被引用が増加するかどうかの研究を紹介)
- 津田 義臣, 「電会議録・会議資料の現状」, 情報の科学と技術,
2005, 55(5), 208-213.
(会議の事前情報, 会議録の書誌)
- 宮明 秀孝, 「国内における医学系会議資料の発行形態の分布」, 情報の科学と技術,
2005, 55(5), 214-218.
(IMIC 学会情報システムの中の情報の分析, 日本医学会文化会 96 学会の予稿集の分析)
- 池田 貴儀, 「科学技術分野における会議録の収集と提供 - 日本原子力研究所図書館の場合」,
情報の科学と技術,
2005, 55(5), 219-223.
(会議録情報入手と提供)
- 新元 公寛, 「OCLC が提供する会議録検索用データベース」, 情報の科学と技術,
2005, 55(5), 224-226.
(ProceedingsFirst)
- 永井 裕子, 「学会が発信する情報 - インターネットによるその変容」,
情報の科学と技術,
2005, 55(5), 227-231.
(学会活動, 大会活動, UniBio Press)
- 中野 明彦, 「学会誌の電子ジャーナル化から冊子体の廃止まで - 日本細胞生物学会
Cell Structure and Function 誌の場合」, 情報管理,
2005, 48(1), 1-6.
(冊子体を廃止して電子ジャーナル一本にした)
- 医薬情報ネット 21 (PINET21), 「これからの治験薬データベースを考える
- その 2 - データベースの機能比較と利用状況調査」, 情報管理,
2005, 48(1), 7-15.
(IDdb, Integrity, Pharmaprojects, R&D Insight, R&D Focus, 明日の新薬)
- 松山 裕二, 寺内 徳彰, 「日本の大学の論文発表: JOIS データベースを使用した計量書誌学的考察」,
情報管理,
2005, 48(1), 16-25.
(雑誌集中度, 共著論文率など)
- 名和 小太郎, 「芸術を法律で裁く - デュシャン注解 -」, 情報管理,
2005, 48(1), 46-47.
(モナリザに口ひげをつけた絵, 「子犬たち」絵葉書事件)
- 桑原 明子, 「情報源ア・ラ・カ・ル・ト 第 6 回 企業情報を探す」,
専門図書館,
2005, (211), 28-33.
(企業名簿, 企業業績, 企業グループ, 企業ランキング, 企業組織, 海外進出,
外国企業, 業種別など)
- 城山 泰彦, 「雑誌購読料金の計量的分析: 掲載論文数, Impact Factor 値,
所蔵館数などの分析を通して」, 医学図書館,
2005, 52(1), 66-71.
(順天堂大学図書館の購読雑誌の分析, 雑誌購読料金の値上がりにもかかわらず,
掲載論文数は減少)
- 野添 篤毅, 園原 麻里, 山下 ユミ, 諏訪部 直子, 牛澤 典子, 「『米国医学図書館協会
(Medical Library Association) 年次大会 2004 年』報告」, 医学図書館,
2005, 52(1), 72-77.
(ワシントンでの大会の参加報告)
- 細野 公男, 「図書館コンソーシアムの現状とその課題」, 情報の科学と技術,
2005, 55(3), 108-113.
(欧米の例, わが国の例)
- 北村 由美, 「東南アジアにおける図書館コンソーシアム」, 情報の科学と技術,
2005, 55(3), 114-118.
(NLDC-SEA, フィリピン, 体, などの例)
- 井上 雅子, 「カナダの図書館コンソーシアム活動」, 情報の科学と技術,
2005, 55(3), 119-123.
(CNSLP の活動)
- 青木 堅司, 永井 夏紀, 「公立大学図書館コンソーシアム活動と ICOLC」,
情報の科学と技術,
2005, 55(3), 124-128.
(2003. 4 に成立したコンソーシアムの活動と ICOLC 参加の経験)
- 中元 誠, 「電子ジャーナル・データベース導入にかかる私立大学図書館コンソーシアム(PULC)の形成について ‐回顧と展望‐」,
情報の科学と技術,
2005, 55(3), 129-131.
(2003. 7 に成立したコンソーシアムの活動)
- 山崎 久道, 戸塚 隆哉, 山本 昭 「座談会:分類を考える」, 情報の科学と技術,
2005, 55(3), 132-140.
(分類/シソーラス/インデクシング部会の活動)
- 永井 裕子, 「日本の学術誌は変革するか -オープンアクセスとの狭間で」,
情報の科学と技術,
2005, 55(3), 141-144.
(日本の SPARC 運動の目指すもの, オープンアクセスの今後)
- 林 和弘, 太田 暉人, 小川 桂一郎 「売れる電子ジャーナルをめざして:
日本化学会の取り組み」, 情報の科学と技術,
2005, 55(3), 145-149.
(日本化学会の J-STAGE を利用した電子ジャーナル発行の経験)
- 飯野 由里江, 「知的財産権に係る判例情報を調べる」, 情報の科学と技術,
2005, 55(3), 150-155.
(特許電子図書館, 裁判所, LEX/DB, e-法規, LEGALBase, LitAlert, Lexis/Nexis,
WestLaw, PACER, アジアの情報など)
- 伊藤 義人, 「アジア諸国における情報サービスの利用 - 第 4 回: 日本 電子ジャーナルコンソーシアム形成と今後の問題点について:
国立大学図書館協会電子ジャーナルタスクフォースの活動」, 情報管理,
2005, 47(12), 786-795.
(タスクフォースの歴史と成果)
- 医薬情報ネット21(PINET21), 「これからの治療薬データベースを考える‐その2 ‐データベースの機能比較と利用状況調査‐上」,
情報管理,
2005, 47(12),796-805.
(Prous, IMS, PJB, Thomson, テクノミック, などのデータベースの機能比較と利用状況)
- 高木 和子, 「世界に広がる機関レポジトリ: 現状と諸問題」, 情報管理,
2005, 47(12), 806-817.
(機関レポジトリの種類, 問題点, ソフトウェア, 実施状況)
- 新保 史生, 「図書館と個人情報保護法」, 情報管理,
2005, 47(12), 818-827.
(図書館が取り扱う個人情報)
- 名和 小太郎, 「QWERTY配列」, 情報管理,
2005, 47(12), 839-841.
(キーボード配列の歴史)
- 荒川 紀子, 「集会報告 第 6 回東南アジア科学技術情報流通 (CO‐EXIST‐SEA)ワークショップ」,
情報管理,
2005, 47(12), 844-847.
(2004. 12. 7-8 に開かれた会議の報告)
- 平間 靖英, 「シンガポールの知的財産ポータル SurfIP」, 情報の科学と技術,
2005, 55(2), 65-71.
(シンガポール知的財産庁が運営する SurfIP について)
- 石井 浩, 「PIUG (Patent Information Users Group, Inc.)の活動」,
情報の科学と技術,
2005, 55(2),72 -75.
(特許情報専門家のフォーラム PIUG は 1988 年に設立, 2003 年の会員数は 250
以上の企業・法律事務所・特許事務所・データベース提供者から 600 以上)
- 殿崎 正明, 「日本の学術雑誌を世界に普及させる必要性とその方法」, 情報の科学と技術,
2005, 55(2), 88-90.
(第 1 回情報プロフェッショナルシンポジウムの講演)
- 松下 茂, 「国内学術雑誌と著作権 ‐課題満載の著作権処理‐」, 情報の科学と技術,
2005, 55(2), 91-93.
(第 1 回情報プロフェッショナルシンポジウムの講演)
- 小川 裕子, 「特許の法的状況を調べる」, 情報の科学と技術,
2005, 55(2), 94-102.
(欧州特許庁の WebRegMT, 米国特許庁の PAIR/IFW, 日本の NRI, INPADOC, IFI,
LitAlert その他)
- 湯川 淳子, 「電子ジャーナル・データベースの管理と運営について(3)」,
薬学図書館,
2005, 50(1), 40-42.
(平成 16 度日本薬学図書館協議会研究集会の討論のまとめ)
- 足立 泰, 「世界最大の抄録・検索データベース: Scopus (スコーパス)」,
薬学図書館,
2005, 50(1), 70-73.
(Elsevier のデータベース Scopus の紹介)
- 植木 譲, 「Derwent Discovery から製薬業界のための統合情報ソリューション
Thomson Pharma へ」, 薬学図書館,
2005, 50(1),74-80.
(Thomson Scientific が提供する Thomson Pharma の紹介)
- 廣瀬 信己, 「Web 情報のデジタル・アーカイビング: WARPを中心に」, 情報管理,
2005, 47(11),721-732.
(国立国会図書館が実施している「インターネット資源選択的蓄積実験事業 (WARP)
の解説)
- 岩崎 治郎, 「電子ジャーナルの価格体系・契約形態の変遷と現在」, 情報管理,
2005, 47(11), 733-738.
(価格設定方式の変遷, 冊子体と電子版, マルチサイト契約, アーカイブ, パッケージ,
コンソーシアム)
- CHU, Jingli; XU, Rujing:著, 澤田 裕子:訳, 「中国科学院文献情報センター」,
情報管理,
2005, 47(11), 739-745.
(中国科学院文献情報センターの情報資源, サービス, 情報研究, 図書館学・情報科学教育)
- 名和 小太郎, 「ガリレオの知的財産観」, 情報管理,
2005, 47(11), 763-764.
(ガリレオの発明「ポンプと給水システム」)
- 野依 良治, 「わが国の科学研究が正当に評価されるために」, 情報管理,
2005, 47(10), 664-638.
(海外誌を通した研究成果発表の問題点, わが国にふさわしい情報発信とは, 国際競争力を持ち得る情報発信とは,
研究成果論文の計量的評価の問題点)
- 遠藤 昌克, 「学術情報検索における,検索エンジン Googleの進出」, 情報管理,
2005, 47(10), 681-687.
(Google と IEEE, Ingenta, Extenza, CrossRef Search, 機関レポジトリなどの関係)
- 中西 博, 「学術情報のIT化への悩み」, 情報管理,
2005, 47(10), 703-705.
(オープンアクセスと IEEE の取り組み)
- 名和 小太郎, 「本の製造物責任」, 情報管理,
2005, 47(10), 706-707.
(「キノコ百科」裁判, 「航空用地図」裁判)
- 小島 陽介, 「電子ジャーナルへのアクセスを管理する図書館用総合サービス」,
情報管理,
2005, 47(10), 708-710.
(電子ジャーナル管理ツール E-Journal A.M.S)
- 愛宕 隆治, 「集会報告: 2004 年 EUSIDIC の秋のコンフェランス」, 情報管理,
2005, 47(10), 711.
(ヘルシンキの EUSIDIC 会議の報告)
- 瀧口 樹良, 「中国の情報化の進展と社会変化」, 情報の科学と技術,
2005, 55(1), 2-5.
(中国のインターネット利用の実態)
- 二階堂 善弘, 「中国のインターネット事情 ‐現状と課題‐」, 情報の科学と技術,
2005, 55(1), 6-9.
(情報収集, 文字コード)
- 張 輝, 「中国における知的財産事情の最新動向 ‐ITとの関わりを踏まえて‐」,
情報の科学と技術,
2005, 55(1), 10-14.
(中国の知的財産法, IT 関連の話題, 上海知的財産パーク構想)
- 川崎 道雄, 「中国における「知識のインフラ」整備事業 ‐清華大学主管の学術情報データベースの概要‐」,
情報の科学と技術,
2005, 55(1), 15-20.
(China National Knowledge Infrastructure (CNKI) とそのデータベース, 中国学術雑誌全文データベース
(CJFD),中国重要新聞データベース (CCND), 中国博士・修士学位論文データベース
(CDMD), 中国重要会議論文データベース (CPCD))
- 菊池 健司 「人物情報」, 情報の科学と技術,
2005, 55(1), 43-44.
(人物情報が得られる Web サイト, 日経 WHO'S WEHO, 日外アソシエーツ Web WHO)
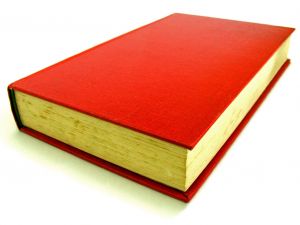 金子務. 「オルデンバーグ
: 十七世紀科学・情報革命の演出者」. 中央公論新社. 2005, 293p.
金子務. 「オルデンバーグ
: 十七世紀科学・情報革命の演出者」. 中央公論新社. 2005, 293p.
(世界最初の雑誌 Philosophical Transactions を創刊したオルデンバーグの仕事)
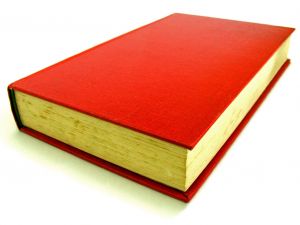 宮田昇. 「 学術論文のための著作権Q&A
: 著作権法に則った「論文作法」」. 新訂版. 東海大学出版会. 2005, 148p.
宮田昇. 「 学術論文のための著作権Q&A
: 著作権法に則った「論文作法」」. 新訂版. 東海大学出版会. 2005, 148p.
-1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, Latest