化学情報, 薬学情報, データベースに関する文献
2007 年 (国内) (国外はこちら)
-1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, Latest
- 時実 象一. 「電子書籍はどこまできたか第234回米国化学会化学情報部会
「化学研究と教育における電子書籍」セッション報告」. 情報の科学と技術.
2007, 57(11), 542-546.
(米国の大学図書館では電子書籍が広く利用されている)
- 浅野 泉,中村 昌弘,田中 弦,糸林真優子,岡崎 知也,日下部光俊,小川 聡.
旭川医科大学学術成果リポジトリAMCoRの構築. 医学図書館.
2007, 54(4), 370-374.
- 小島 浩子. 信州大学医学部図書館におけるメディカルオンラインの利用動向と効果.
医学図書館.
2007, 54(4), 375-379.
- 名和 小太郎.
データ保護 対 監視 情報管理.
2007, 50(8), 525-526.
()
- 田村 善之. バイオテクノロジーと特許制度のあり方:
第3回:情報化したバイオ特許の権利行使の制約原理. 情報管理.
2007, 50(7), 403-409.
(権利侵害に対して差止めを認めず,損害賠償のみを請求しうる法理の活用の可能性)
- 西山 真, 加藤 久典, 吉田 稔, 山口 五十麿, 宮川 都吉, 小鹿 一, 小梅枝
正和, 日岡 康恵, 電子投稿審査システムの導入とその影響:日本農芸化学会の経験.
情報管理.
2007, 50(7), 429-436.
(2005/6 に J-STAGE の投稿審査システムを導入した)
- 治部 眞里, 近藤 隆. JST
ReaD における科学技術人材の流動性に関する考察. 情報管理.
2007, 50(7), 437-445.
(ReaD に登録された60,553人の研究者の流動性の状況を分析)
- 宮入 暢子. 科学の世紀:Web
of Science?からよみとる日本の20世紀科学研究. 情報管理.
2007, 50(7), 446-456.
(Web of Science を利用し日本の科学者の研究を調査)
- 名和 小太郎.
特許「私自身」 情報管理.
2007, 50(7), 461-462.
()
- 後藤 敏行. 電子ジャーナルのアーカイビング:論点,動向,将来展望.
圖書館界. 2007. 58(6), 320-331.
(Portico, オランダ国立図書館、LOCKSS など)
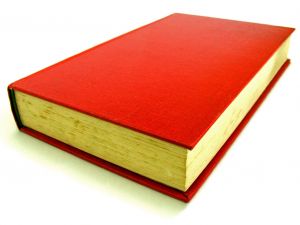 山崎 茂明. 「パブリッシュ・オア・ペリッシュ」.
みすず書房. 2007. 11, 163 pp., 2800 円.
山崎 茂明. 「パブリッシュ・オア・ペリッシュ」.
みすず書房. 2007. 11, 163 pp., 2800 円.
- 発表するか、それとも死か
- 公正な科学研究が私たちの生活を支える
- 求められたヒーロー
- 一番をめざす
- 私は不正な実験に関与していない
- 成果へのプレッシャー
- インパクトファクターで研究者を評価できるか
- なせ゜著者サインを偽造したのか
- なぜ私の論文が盗用されたのか
- オーサーシップ
- レフェリーシステムを再構築する
- 不正行為を考える
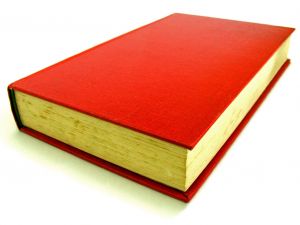 藤田 節子. 「キーワード検索がわかる」.
筑摩書房. 2007. 10, 188 pp., 720 円.
藤田 節子. 「キーワード検索がわかる」.
筑摩書房. 2007. 10, 188 pp., 720 円.
- キーワードとは
- 情報検索とは
- キーワードの選択法
- 全文キーワード法
- 統制キーワード法
- 基本的検索機能
- 適切なキーワードを見つけるテクニック
- 情報の信頼性と著作権
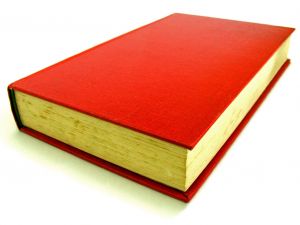 倉田 敬子. 「学術情報流通とオープンアクセス」.
勁草書房, 2007. 8, 196 pp., 2600 円.
倉田 敬子. 「学術情報流通とオープンアクセス」.
勁草書房, 2007. 8, 196 pp., 2600 円.
- 情報メディアから見る学術コミュニケーション
- 学術情報の特性と学術情報流通モデル
- 学術雑誌
- 学術論文の機能と構成
- 電子ジャーナル
- オープンアクセスとは何か
- 清水美都子. 「特許電子図書館」を利用した特許調査の可能性 . オンライン検索.
2007, 28(3), 103-122.
- 澤井 清. 国文学のデータベース -国文学論文目録データベース- . オンライン検索.
2007, 28(3), 123-138.
- 阿部信一. PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholarの比較 . オンライン検索.
2007, 28(3), 139-140.
- 難波 英嗣. 「知財活用の実際
論文と特許データベースを統合したジャンル横断検索および技術動向分析」.
情報の科学と技術.
2007, 57(10), 483-487.
(特許と論文を対象にした検索や技術動向分析に関する諸研究を概観し,関連システムやサービスを紹介)
- 桐山 勉. 「関西特許情報センター振興会創立50周年記念事業
特許検索競技大会開催報告」. 情報の科学と技術.
2007, 57(10), 493-499.
(2007/7/27 に開催された「特許検索競技大会」の報告)
- 筑木 一郎. 「学術情報流通と大学図書館の学術情報サービス」.
カレントアウェアネス. 2007/9/20, (293), CA1639.
(購読、ナビゲーション、契約管理、電子ジャーナル化、機関リポジトリなど)
- 渡部満彦. 教育学データベースERIC . オンライン検索.
2007, 28(2), 47-61.
- 西中山 隆. 国立国会図書館インターネット情報アーカイブ事業「WARP」のご紹介
. オンライン検索.
2007, 28(2), 62-74.
- 古関美津子. Clinical Evidenceはどう使うか . オンライン検索.
2007, 28(2), 75-82.
- 佐々木陽子. BMJ Clinical Evidenceプロダクトレビュー . オンライン検索.
2007, 28(2), 83-91.
- 田村 善之. バイオテクノロジーと特許制度のあり方:
第2回:バイオ特許の情報化とその限界. 情報管理.
2007, 50(6), 317-321.
(どの程度,技術開発が具体化すれば特許を認めてよいのか)
- 渡邊 由紀子. 大学図書館における電子リソース・サービスの推進―九州大学附属図書館のコンテンツ整備・きゅうとサービス・組織再編―.
情報管理.
2007, 50(6), 343-353.
(リンクリゾルバ,電子ジャーナル集,OPAC など電子的サービスを相互に連携)
- 植松 利晃. 情報検索における漏れのない検索に着目したJST文献検索システム「JDreamII」の検索支援機能の紹介.
情報管理.
2007, 50(6),354-362.
(統制語索引,JSTシソーラスブラウザ,異表記自動展開機能,機関名ブラウザ)
- 志村 勇. 企業からみた情報の変遷とサーチャーに対する期待.
情報管理.
2007, 50(6), 363-366.
()
- 名和 小太郎.
隔離された科学,そして科学研究 SOX 法 情報管理.
2007, 50(6), 367-368.
()
- 独立行政法人 科学技術振興機構 文献情報部 辞書課.
化学物質リンクセンタープロトタイプ版〜関連する化学物質情報をワンストップで〜
情報管理.
2007, 50(6), 369-373.
()
- 時実 象一.
集会報告: 学術出版協会 (Society for Scholarly Publishing) 年会: Society
for Scholarly Publishing 29th Annual Meeting 情報管理.
2007, 50(6), 374-383.
(San Francisco でおこなわれた年会の報告)
- 栗山 和子. 「情報検索システムの評価
: テストコレクションを中心に」. 情報の科学と技術.
2007, 57(8), 378-383.
(テストコレクションと評価指標)
- 広瀬 容子, 中澤 夏子. 「引用データを用いたジャーナルコレクション評価の手法」.
情報の科学と技術.
2007, 57(8), 396-403.
(トムソンサイエンティフィックの Citation Index 製品に収録される引用データを用いてのジャーナルコレクション評価の手法)
- 田村 善之. バイオテクノロジーと特許制度のあり方:
第1回:問題の所在. 情報管理.
2007, 50(5), 251-257.
(より早期の開発の段階で,いまだ技術が抽象的なものにとどまっている段階で,特許保護を求める動きがある)
- 植村 八潮. 「多様な著作権」と「一つの著作権制度」をめぐって.
情報管理.
2007, 50(5), 285-287.
()
名和 小太郎.
領空か 宇宙空間か 情報管理.
2007, 50(5), 288-290.
()
- 中井 万知子. 日本の全国書誌サービス─その歩みと展望.
情報管理.
2007, 50(4), 193-200.
(国立国会図書館(NDL)の『日本全国書誌』)
- 大蔵 聡. 日本繁殖生物学会におけるJ-STAGE投稿審査システム導入事例:
Journal of Reproduction and Development(JRD)誌のオンライン投稿審査システム.
情報管理.
2007, 50(4), 201-209.
(2006. 1 より J-STAGE の投稿審査システムを導入)
- 冨永 祥平. 索引作業におけるより高度な支援辞書の利用〜JST抄録・索引支援システム「NAISS」について〜.
情報管理.
2007, 50(4), 210-217.
(JST のデータベース作成の抄録・索引支援システム「NAISS」)
名和 小太郎.
サルにもできる? 情報管理. 2007, 50(4), 225-226.
()
- 小山 順一郎. ISSN
(国際標準逐次刊行物番号),ISSN ネットワークと日本センター:紹介と今後の課題について.
情報管理.
2007, 50(3), 144-154.
(ISSN の解説)
- 古谷 実. 改訂された「参照文献の書き方」―SIST
02 2007年版について―. 情報管理.
2007, 50(3), 155-161.
(参照文献の書き方の基準が変更された)
- 菅野 育子. 書誌記述における雑誌名と機関名の扱い:
SIST 05,SIST 06の改訂による完全表記. 情報管理.
2007, 50(3), 162-166.
(雑誌名と機関名については完全表記が求められる)
- 名和 小太郎.
サルのタイプライター理論. 情報管理.
2007, 50(3), 175-176.
()
- 殿先正明. 日本の医学関係書誌データベースの統一を願って . オンライン検索.
2007, 28(1), 1-2.
- 白土裕子. 「医学用語シソーラス第6版」の紹介と医中誌Webにおけるシソーラスの役割
. オンライン検索.
2007, 28(1), 3-11.
- 設楽真理子. QUOSA Information ManagerTM-まったく新しいフルテキスト管理ツール
. オンライン検索.
2007, 28(1), 12-20.
- 阿部信一. Drugs and Lactation Database(LactMed)-http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT
. オンライン検索.
2007, 28(1), 21-22.
- 阿部信一. 医学略語のMeSHへのマッピング . オンライン検索.
2007, 28(1), 23-24.
- 手島 正行, 大坂 要恵, 白鳥 耕也, 畠山 義朗, 佐々 齋. 「化粧品安全性関連情報の収集について
: フォーカスサービスを利用した文献情報の効率的収集法」. 情報の科学と技術.
2007, 57(6), 281-286.
(ジー・サーチ社のフォーカスサービス (SDI文献管理ポータルサイト) の資生堂社における経験)
- 越久村 浩司. 「安全性情報収集サービスと医薬品安全性文献データベース
: JAPIC-Q サービス, iyakuSearch, JAPICDOC, SOCIE」. 情報の科学と技術.
2007, 57(6), 287-291.
(JAPIC のサービスの紹介)
- 田中 早苗. 「医薬品安全情報のオンラインデータベースでの検索テクニック」.
情報の科学と技術.
2007, 57(6), 292-297.
(Dialog の MEDLINE, EMBASE, Dialog Alerts の効果的な使い方)
- 佐藤 京子, 西岡 文美. 「受託安全確保業務
: GVP省令に基づく医薬品・医療機器等の情報収集について」. 情報の科学と技術.
2007, 57(6), 298-303.
((財)国際医学情報センターの GVP 省令に基づく「学会報告,文献報告その他の研究報告に関する情報の収集」業務)
- 中塚 真依子. 「医薬品の安全性監視における文献の重要性
: Thomson Scientific Custom Information Services (CIS)の視点から」.
情報の科学と技術.
2007, 57(6), 304-309.
(トムソンサイエンティフィックの Custom Information Services の紹介)
- 安岡 孝一. ケータイの絵文字と文字コード.
情報管理.
2007, 50(2), 67-73.
(ケータイの絵文字は各社毎にコードが異なっている)
- 後藤 敏行. デジタル情報保存のためのメタデータ:現状と課題.
情報管理.
2007, 50(2), 74-86.
(PREMIS について)
- 山崎 茂明. 19
世紀フィラデルフィア医学ジャーナリズムの展開. 情報管理.
2007, 50(2), 87-96.
(1804年に,CoxeがPhiladelphia Medical Museum、BartonがPhiladelphia Medical
and Physical Journalを、1820年には,Nathaniel ChapmanがPhiladelphia Journal
of the Medical and Physical Sciencesを創刊、これは後にAmerican Journal
of the Medical Sciencesへと発展)
- 名和 小太郎. バグなし,デバグあり.
情報管理.
2007, 50(2), 103-104.
()
- 須賀 万智. 科学論文作成における文献管理ソフトEndNoteの活用 (特集 文献管理).
医学図書館,
2007, 54(3), 229-231.
- 坂内 悟. 「JDreamPetit利用者の検索行動から考察した一般市民の医療情報へのニーズ」.
医学図書館,
2007, 54(2), 155-159.
(個人利用 55%、「医療と生活」カテゴリーが 30%、「ナノテクノロジー」が 22%)
- 時実 象一. 「電子ジャーナルのオープンアクセスと機関リポジトリ−どこから来てどこへ向かうのか (II)機関リポジトリと研究助成機関の動向」.
情報の科学と技術.
2007, 57(5), 249-255.
(大学・研究機関リポジトリの動向,著作権の問題,設置・運用状況,コンテンツの検索,
の運用経験, 研究助成機関のオープンアクセス支援, NIH, FRPAA, Wellcome 財団,
RCUK)
- 時実 象一. 「
中国における電子ジャーナルの現状」. 情報管理.
2007, 50(1), 2-10.
(China National Knowledge Infrastructure: CNKI、Wanfang Data、VIP Information
について)
- クリム ナオミ, 鈴木 英明:訳, 松下 茂:訳. 「
カナダ国立科学技術情報機関CISTI 情報格差を埋めるために」. 情報管理.
2007, 50(1), 11-19.
(CISTI はカナダの化学情報図書館として文献複写サービスその他をおこなっている。CISTIの一部門、NRC
Research Pressは,16誌の国際研究雑誌と書籍や会議録を刊行している)
- 和田 光俊, 時実 象一, 田口 友子. 「
J-STAGE登載電子ジャーナルへのアクセス動向の分析」. 情報管理.
2007, 50(1), 20-31.
(ジャーナル282誌,約11万件の論文について,アクセス動向の分析を行った)
- 荒川 紀子. 「
J-STAGE購読機関への利用統計レポートの提供開始とCOUNTER準拠」. 情報管理.
2007, 50(1), 32-39.
(J-STAGE は 2006 年末に COUNTER に準拠した)
- 戸田 裕二. 「
企業の知的財産マネジメントにおける特許・技術情報の管理と活用」. 情報管理.
2007, 50(1), 44-46.
(特許・技術情報の管理と活用、社内特許・技術情報管理、リスク分析、など)
- 名和 小太郎. 「
円周率の使用料」. 情報管理.
2007, 50(1), 47-48.
(1897 年インディアナ州議会の円周率に関する法律)
- 松岡 資明. 「アーカイブズと図書館」. 情報の科学と技術.
2007, 57(4), 174-179.
(アーカイブズの役割と直面する問題)
- 牧野 友衛,徳生 裕人. 「グーグルブック検索の取組みについて」. 情報の科学と技術.
2007, 57(4), 174-179.
(Google Book Search について)
- 時実 象一. 「電子ジャーナルのオープンアクセスと機関リポジトリ−どこから来てどこへ向かうのか (I)オープンアクセス出版の動向」.
情報の科学と技術.
2007, 57(4), 198-204.
(Directory of Open Access JournalsやPubMed Centralの雑誌の分析,BioMed
CentralやPLoSなどのオープンアクセス雑誌,HighWire Pressなどの時差公開,掲載料を支払って自分の論文をオープンアクセスとするオープンアクセス・オプション)
- 三浦 誠. 「日本三大死因をキーワードとして抽出した被引用回数上位論文のPubMedにおけるPublication
Types調査:EBMとの相関を中心に」. 医学図書館,
2007, 54(1), 63-68.
(悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、の被引用上位文献)
- 藤田 節子, 「
国内人文・社会科学系学会誌の投稿規定の分析 (II)」, 情報管理,
2007, 49(11), 622-631.
(参照文献の書き方、著者抄録、キーワード、著作権、別刷・掲載料等、電子投稿などの項目について比較分析)
- 岡本 真, 「
「Web2.0」時代に対応する学術情報発信へ真のユーザー参加拡大のためのデータ開放の提案」,
情報管理,
2007, 49(11), 632-643.
(Web 2.0、ブログ、学術情報)
- 結城 智里, 「
インターネット情報から抜け落ちた過去を現在につなぐ『企業名変遷要覧』のデータ作成を通して考えたこと」,
情報管理,
2007, 49(11), 644-655.
(機械工業図書館における「企業名変遷要覧」編集の経験)
- 高野 明彦, 「
コンテンツを発想力に換える連想計算」, 情報管理,
2007, 49(11), 656-658.
(連想エンジン GETA と情報サービス「想・IMAGINE」)
- 名和 小太郎, 「
プログラムは言論か」, 情報管理,
2007, 49(11), 659-660.
(ダニエル・J・バーンスタインが暗号化システムの学会公表を「武器国際輸送規制
(ITAR)」によって差し止められた事件)
- 林 和弘「理工医学系電子ジャーナルの動向
- 研究情報収集環境と事業の変革」. 科学技術動向. 2007, (2), 17-29.
(研究活動における電子ジャーナルの役割、事業としてみた電子ジャーナル、電子ジャーナルが日本の学協会に与えた影響、日本発の電子ジャーナルおよび情報流通を改善するための提案、電子ジャーナル出版組織の統合と日本型非営利出版活動の模索)
- 岸田 和明. 「インターネット時代における統制語彙の意義と役割」.
情報の科学と技術.
2007, 57(2), 62-67.
()
- 上野 京子. 「SciFinder-トピック検索の裏側」.
情報の科学と技術.
2007, 57(2), 68-72.
(トピック検索では入力した検索語にさまざまな処理がなされる)
- 嶋田 真智恵. 「国立国会図書館件名標目表(NDLSH)の改訂作業と今後について」.
情報の科学と技術.
2007, 57(2), 73-78.
(2004 年から改訂作業に取り組む)
- 棚橋 佳子, 宮入 暢子. 「統制語索引と自然語検索を補完するCitation
Semanticの効用」. 情報の科学と技術.
2007, 57(2), 79-83.
(Web of Science の KeyWords Plus と Related Records)
- 佐藤 久光. 「ExpressFinder/シソーラス辞書開発の目的および基本ルール」.
情報の科学と技術.
2007, 57(2), 84-88.
(エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジの EF/シソーラス)
- マーカム ディアンナ, 「
ワールド・デジタル・ライブラリーは実現するか」, 情報管理,
2007, 49(10), 542-554.
(2006. 7. 6 の金沢工業大学での「図書館・情報科学に関する国際ラウンドテーブル会議」での講演、図書の電子化、Google
Book Project など)
- 大田 朋子, 「
自然言語処理技術に基づく意味構造を利用した情報検索と情報抽出: MEDIEとInfo-PubMed」,
情報管理,
2007, 49(10), 555-563.
(MEDLINE を用いて、構文解析によって計算された意味構造を用いて,関係概念を検索・抽出するシステムを構築)
- 藤田 節子, 「
国内人文・社会科学系学会誌の投稿規定の分析 (I)」, 情報管理,
2007, 49(10), 564-575.
(投稿者の資格、論文の種類、論文の言語、論文の受理・採用日、書式、図表・写真、学術用語、量記号・単位記号、数式などの項目について比較分析)
- 生貝 直人, チェン ドミニク, 松本 昴, 野口 祐子, 「
クリエイティブ・コモンズの進化と変容: ビジネスモデルとWeb2.0を巡って」,
情報管理,
2007, 49(10), 576-585.
(クリエイティブ・コモンズはライセンスの活用によるビジネスモデルの形成に重点が移っている)
- 岡本 真, 「
学術研究プラットフォームとしてのネットサービスを夢見る―新たな学術コミュニティーと学術コミュニケーションに向けて」,
情報管理,
2007, 49(10), 586-588.
(研究者個人が参加するプラットフォームの提案)
- 名和 小太郎, 「
スライドは「印刷物」か」, 情報管理,
2007, 49(10), 589-590.
(スライドで発表された知見は公知となるか)
- 林水紀 . JCRを利用した園芸学(Horticulture)分野の2ステップマップ作成
. 日本農学図書館協議会誌.
2007, (144), 7-12.
- 田中法子 . JCRを活用したForestry分野2ステップマップ . 日本農学図書館協議会誌.
2007, (144), 1-6.
- 富田健市 . 日本の学協会における著作権の取扱い等について-機関リポジトリへの対応を中心として-
. 大学図書館研究.
2007, (79), 1-8.
- 鈴木宏子 . 構築5年,運用2年目の機関リポジトリ-千葉大学CURATORの今- .
大学図書館研究.
2007, (79), 9-17.
- 橋洋平 . 金沢大学学術情報リポジトリKURAの構築と課題 . 大学図書館研究.
2007, (79), 18-26.
- 酒見佳世, 五十嵐健一 . 慶応義塾大学機関リポジトリ(KOARA)のシステムとメタデータ
. 大学図書館研究.
2007, (79), 27-34.
- 尾崎文代, 上田大輔 . 広島大学学術情報リポジトリ(HiR)のコンテンツ収集戦略-機関リポジトリを育て続けるために-
. 大学図書館研究.
2007, (79), 35-42.
- 赤崎久美, 山本和雄. 国際図書館コンソーシアム連合(ICOLC:International
Coalition of Library Consortia)2006年秋季会合参加報告 . 大学図書館研究.
2007, (79), 68-77.
- 三根慎二 . オープンアクセスジャーナルの現状 . 大学図書館研究.
2007, (80), 54-64.
- 高辻 功一, 大前 冨美. 電子ジャーナル導入によるNACSIS-ILL経由の文献複写依頼件数の減少効果
: 大阪府立大学における調査. 大学図書館研究.
80, 74-78, 2007-08.
- 高橋 菜奈子. NACSIS-CATにおける韓国・朝鮮人著者名典拠の同定. 大学図書館研究.
80, 65-73, 2007-08.
- 竹井 弘樹. 「韓国のネット利用と図書館情報化事情」. 情報の科学と技術.
2007, 57(1), 26-33.
(韓国の IT 政策、デジタル図書館構築事業、デジタル図書館の実例 (石水図書館)
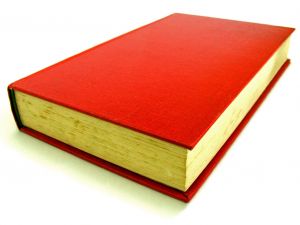 日本図書館情報学会研究委員会.
「学術情報流通と大学図書館」. 勉誠出版. 2007, 217p.
日本図書館情報学会研究委員会.
「学術情報流通と大学図書館」. 勉誠出版. 2007, 217p.
- 学術情報流通の現況
- 日本における学術情報流通基盤整備に向けての活動
- 大学図書館の役割と課題
-1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, Latest