化学情報、薬学情報、データベースに関する文献
2004 年 (国内) (国外はこちら)
-1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, Latest
- 筑木 一郎. 「英米両国議会における学術情報のオープンアクセス化勧告」.
カレントアウェアネス. 2004/12/20, (282), CA1544.
(英国下院科学技術委員会の勧告、および米国 NIH の計画案についての議会の動向)
- 芳鐘 冬樹. 「科学研究出版の費用分析とビジネスモデル」.
カレントアウェアネス. 2004/12/20, (282), CA1543.
(論文出版にはどの程度の費用がかかるかについての研究を紹介)
- 藤田 節子, 「公益法人の専門図書館における複写サービス」、専門図書館,
2004, (210), 31-38.
(図書館法第 2 条第 1 項私立図書館としてであれば、複写サービスが可能となる)
- 宮本 光一郎, 「情報源ア・ラ・カ・ル・ト: 第 5 回 国内の統計を探す」、専門図書館,
2004, (210), 39-45.
(官庁統計、業界統計民間統計、オンラインデータベースなど)
- 依田 紀久, 「国立国会図書館レファレンス共同データベース実験事業の取り組み」、専門図書館,
2004, (209), 16-24.
(レファレンス事例のインターネットでの公開、事例データベースなど)
- 桑原 明子, 「情報源ア・ラ・カ・ル・ト 第 4 回 情報リテラシー教育を実践するための情報源」、専門図書館,
2004, (209), 29-34.
(探し方、ガイダンス、など)
- 藤田 節子, 「図書館における著作物の利用に関する権利者との話し合い
- 経過報告」、専門図書館,
2004, (207), 31-36.
(権利者との話し合い経過、当事者協議、新当事者協議会)
- 松下 茂, 「国内外の利用者の取り組みについて」、専門図書館,
2004, (207), 37-41.
(国内の著作権処理機関の現状と問題点)
- 南 亮一, 「図書館に関係する著作権法改正の動向」、専門図書館,
2004, (207), 42-49.
(複写、上映、貸し出しなど)
- 荒居 万里子, 「海外電子情報購入のノウハウ」、専門図書館,
2004, (207), 50-55.
(ジェトロでは海外データベースなどの購入に年間 6000 万円を使っている)
- 堀木 和子, 「効果的な電子ジャーナルの導入 - 国立大学の例」、専門図書館,
2004, (207), 56-65.
(名古屋大学の例)
- 鈴木 祐介, 「米国における ILL サービスの現状: イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の事例」、大学図書館研究,
2004, (72), 36-40.
(ILL の動向、現状、UIUC での ILL)
- 前田 弘子, 青木 堅司, 井上 修, 「国際図書館コンソーシアム連合 (ICOLC:
International Coalition of Librayr Consortia) 第 15 回会合参加報告」、大学図書館研究,
2004, (72), 58-68.
(会議の詳細、日本からはむ IPAP の谷藤氏が発表)
- 大関 玲子, 田中 文恵, 小林 浩樹, 沖 愛子, 「『科学技術情報検索の実際』テキスト作成:
東京農工大学での事例報告」、大学図書館研究, 2004, (71), 41-48.
(科学技術情報と電子図書館、データベース、電子ジャーナル、PATOLIS、遺伝子情報・タンパク質データベース、インターネット情報、図書館での情報検索の実際)
- 尾城 孝一, 松本 和子, 井上 修, 「国際図書館コンソーシアム連合 (ICOLC:
International Coalition of Librayr Consortia) 第 14 回会合参加報告」、大学図書館研究,
2004, (71), 49-55.
(会議の詳細)
- 山本 和雄, 「欧州国際図書館コンソーシアム連合 (E-ICOLC: International
Coalition of Librayr Consortia in Europe) 第 5 回会合参加報告」、大学図書館研究,
2004, (71), 49-55.
(会議の詳細)
- 増田 豊, 「私の回顧録: SilverPlatter と Ovid の歴史を振り返る」, オンライン検索,
2004, 25(3, 4), 140-149.
(CD-ROM の誕生と CD-ROM データベース、SilverPlatter と Ovid, PubMed の誕生など)
- 岩沢 一男, 「「オンライン検索」創刊 25 年に寄せて」, オンライン検索,
2004, 25(3, 4), 150-158.
(データベース数の推移や検索機能など、オンライン検索の歴史)
- 福林 靖博, 「国立国会図書館「レファレンス情報システム」について」,
オンライン検索, 2004, 25(3, 4), 167-177.
(参考図書、論文集、資料集、会議録など 40,471 冊のコンテンツが検索可能、目次情報も入っている)
- 大崎 泉, 「EMBASE.com Ver.4.2 の機能と特性」, オンライン検索, 2004,
25(3, 4), 178-184.
(収載誌数 6000 以上、データ数 1600 万件以上)
- 田代 朋子, 「医薬系シソーラス辞書 「T辞書」の構造と特徴」, オンライン検索,
2004, 25(3, 4), 197-205.
(特定のデータベース用ではなく、汎用性を目的とした医学辞書)
- 足立 泰, 「世界最大の学術ナビゲーション・データベース: Scopus (スコーパス)」,
オンライン検索, 2004, 25(3, 4), 206-214.
(4000 社からの 14,000 タイトルを収録、検索機能、引用ナビゲーションなどを紹介)
- 細井 宏朗, 「オンラインジャーナル総合検索/購読管理サービス」, オンライン検索,
2004, 25(3, 4), 215-224.
(SwetsWise online content の紹介)
- 梅原 成子、「情報源アラカルト 第 3 回 法情報を探す」、専門図書館、2004,
(208), 47-515.
(参考図書、法令、ウェブ検索、官報など)
- 山田 知子,阿部 信一, 「EMB情報源における緊急医療情報への対応」, 薬学図書館、2004,
49(4), 240-245.
(The Cochrane Library, Clinical Evidence, UpToDate)
- 上村 圭介, 「クリエイティブ・コモンズによる「自由に共有できるコンテンツ」とオープンアクセス」,
薬学図書館、2004,
49(4), 246-251.
(Creative Commons の目的と背景、共有できる権利と義務、共有条件の表明)
- 松下 茂, 「学術情報流通の新しいトレンド:オープンアクセスの現状について」,
薬学図書館、2004,
49(4), 252-255.
(オープンアクセスの定義、広がり、出版者の対応、評価と将来)
- 向田 厚子、「The New England Journal of Medicineにおける被訂正論文のインパクト」、医学図書館、2004,
51(4), 357-362.
()
- 長塚 隆, 「情報検索の技術動向」, 情報の科学と技術,
2004, 54(12), 624-628.
(Asilomar レポート、Lowell レポート、情報検索の技術動向、情報検索サービスにおける技術動向)
- 高野 明彦, 西岡 真吾, 丹羽 芳樹, 「連想に基づく情報アクセス技術 -汎用連想計算エンジン
GETA を用いて-」, 情報の科学と技術,
2004, 54(12), 634-639.
(連想計算と連想検索、NII の Webcat Plus、文化遺産オンライン、新書マップ)
- 横井 俊夫, 「セマンティック Web -コンピュータが理解できるメタデータ-」,
情報の科学と技術,
2004, 54(12), 640-646.
(目標と目的、全体像、メタデータ記述の枠組み、語彙の意味理解)
- 江口 浩二, 「Web 情報アクセス技術の評価モデル」, 情報の科学と技術,
2004, 54(12),647-652.
(Web 検索の評価モデルと評価ワークショップ)
- 菊地 哲也, 「ニュース情報を調べる」, 情報の科学と技術,
2004, 54(12), 653-657.
(インターネットのホームページ、データベース)
- 末廣 恒夫、「神奈川県資料室研究会と神奈川県立川崎図書館 - 新たな協力関係に向けて
-」、専門図書館、(206),
1-5, 2004.
()
- 阿部 信一、「MEDLINEの検索方法の分析研究: 海外文献のレビュー」、医学図書館、51(3),
221-229, 2004.
(McMaster 大学の研究、効果的な検索方法に関する研究、ハンドサーチとの比較、他のデータベースとの比較、MeSH
と自由語の比較)
- 牛澤 典子、「Web of Science」、医学図書館、51(3),230-233,
2004.
(Science Citation Index と Web of Science の紹介)
- 大野 彩、「日本医科大学図書館における DialogWeb の提供状況」、医学図書館、51(3),
234-238, 2004.
(DialogWeb の紹介と利用の解析)
- 山崎 静香, 谷川原 祐介、「MICROMEDEX Healthcare Series」、医学図書館、51(3),
239-242, 2004.
(医薬品情報、中毒情報の MICROMEDEX Healthcare Series の紹介)
- 児玉 閲、「フルテキスト・データベースとしての EBSCOhost Biomedical
Reference Collection」、医学図書館、51(3),243-247,
2004.
(EBSCOhost Biomedical Reference Collection の紹介と杏林医科大学の利用状況)
- 澤 典子、「関西医科大学におけるMD Consultの利用」、医学図書館、51(3),248-253,
2004.
(MD Cosult の紹介と利用経験)
- 今野 穂、「電子コンテンツ管理における札幌医科大学附属図書館の取り組み:
MetaLib/SFX 導入経験を中心に」、医学図書館、51(3),254-260,
2004.
(MetaLib/SFX, Resolver モデル、運用状況、OpenURL 対応)
- 加賀美 祐介、「Links@Ovid: 統合学術プラットフォームとしての Ovid」、医学図書館、51(3),261-265,
2004.
(Links@Ovid の紹介)
- 殿崎 正明、「日本医学図書館協会の法人化とその活動」、医学図書館、51(3),266-270,
2004.
(NPO 法人化の経緯とそのメリット)
- 村上 晴美,平田 高志,上田 洋, 「Subject World -主題の世界 -」, 情報の科学と技術,
2004, 54(11), 568-574.
(検索結果のビジュアル化ツール)
- 宮入 暢子, 「特許引例の視覚化における考察 - ビブリオメトリクス概念の活用」,
情報の科学と技術,
2004, 54(11), 575-581.
(特許のサイテーションマップ)
- 及川 光博, 「インタラクティブなデータ視覚化環境」, 情報の科学と技術,
2004, 54(11), 589-595.
(Spotfire, DecisionSite)
- 重田 有美, 「規格の検索」, 情報の科学と技術,
2004, 54(11), 611-616.
(ISO, IEC, ITU, CEN, JIS など)
- 日暮 理加, 「MSDS情報」, 情報の科学と技術,
2004, 54(10), 541-545.
(インターネット上の MSDS 情報)
- 福山 秀敏. 「なぜ国内誌?」. 日本物理学会誌,
2004, 59(9), 622-624.
(J. Phys. Sco. Jpn. を発行する意義)
- 佐宗 哲郎, 西森 秀稔, 斯波 弘行. 「JPSJ の現状と将来」. 日本物理学会誌,
2004, 59(9), 624-627.
(J. Phys. Sco. Jpn. の投稿・掲載の現状、編集体制の改革)
- 九後 太一, 二宮 正夫. 「プログレスの現状と将来」. 日本物理学会誌,
2004, 59(9), 627-630.
(Progress of Theoretical Physics の沿革と今後の展望)
- 鈴木 徹, 伊東 一良. 「JJAP の現状と将来 - JPSJ の兄弟誌として」.
日本物理学会誌,
2004, 59(9), 630-637.
(J. Jpn. Appl. Phys. の現状と今後の対策)
- ヒーリー,レイ・ワトソン, 「進化するコンテンツ利用者 - 新しいタイプの利用者の役に立つために図書館はどのように変化すべきか」、情報管理、2004,
47(9), 579-592.
(情報検索利用者のプロファイル)
- HAANK, Derk, インタビューア・記事執筆 POYNDER, Richard, 「- 前進かやめるか
- (翻訳記事)」、情報管理、2004,
47(9), 593-599.
(Springer Verlag 社長の Derk Haank のインタビュー)
- TURNER, Rollo, 高木 和子:訳, 「チャレンジについて率直に語る: インターメディアリーの役割,機能,今後」、情報管理、2004,
47(9), 600-609.
(購読代理店の役割)
- 時実 象一, 「オープンアクセスの動向」、情報管理、2004,
47(9), 616-624.
(オープンアクセスの歴史、オープンアクセス雑誌、機関レポジトリ、出版者の対応)
- 名和 小太郎, 「図書館におけるフィルタリング」、情報管理、2004,
47(9), 636-638.
(米国子供インターネット保護法 (Children's Internet Protection Act (CIPA)
について)
- 宇田川 信生, 「レファレンス資料の統合検索サービス: xreferplus (エックス・リファー・プラス)」、情報管理、2004,
47(9), 639-643.
(参考資料の統合検索)
- 宮入 暢子, 「"高品質な学術情報の収録のために: ジャーナル選択の基準゛抄訳および解説」、情報管理、2004,
47(9), 644-648.
(Thomson Scientific (ISI) の Science Citation Index における雑誌選択基準)
- YAO, XiaoXia; CHEN, Ling:著, 澤田 裕子:訳, 「アジア諸国における情報サービスの利用
- 第3回:中国 CALIS の概要 -」、情報管理、2004,
47(8), 528-534.
(中国学術図書館・情報システム (CALIS) の歴史とサービス)
- クレシュ, ダイアン;ゴッテスマン, ローラ:著, 高木 和子:訳,「QuestionPoint:
米国議会図書館と OCLC の共同 - 最新情報」、情報管理、2004,
47(8), 535-540.
(共同レファレンス・サービスの試み)
- 前田 知子, 「"Science.gov゛米国連邦政府関係機関による科学技術ポータル」、情報管理、2004,
47(8), 541-546.
(Science.gov の紹介)
- 名和 小太郎, 「共著者は増える」、情報管理、2004,
47(8), 556-557.
(共著者、共同発明者、儀礼的な共著者)
- 足立 泰, 「学術情報ナビゲーションサービス; Scopus(スコーパス)」、情報管理、2004,
47(8), 558-562.
(Elsevier のデータベース Scopus の紹介)
- 時実 象一, 「米国化学会情報化学部会報告」, 情報管理,
2004, 47(8), 563-566.
(オープンアクセスに関する討論)
- 玉田 俊平太, 児玉 文雄, 玄場 公規, 「重点 4 分野におけるサイエンスリンケージの計測
(下) - そのインプリケーションと限界 -」、情報管理、2004,
47(7), 455-462.
(特許に引用されている論文等の数を計測)
- PAUL Johnson・著, 加藤 多恵子・訳,「アジア諸国における情報サービスの利用 -
第2回:シンガポールにおける図書館 -」、情報管理、2004,
47(7), 463-470.
(シンガポール図書館の動向)
- 齋藤 久実子, 「神奈川県立川崎図書館における「科学技術系外国語雑誌デポジット・ライブラリー」の開設」、情報管理、2004,
47(7), 476-480.
(県立川崎図書館、神奈川県資料室研究会、デポジット・ライブラリ)
- 京本 直樹, 「東京工業大学の知的財産マネジメントプログラムについて」、情報管理、2004,
47(7), 488-494.
(大学院教育プログラム)
- 名和 小太郎, 「特許 対 公序」、情報管理、2004,
47(7), 498-499.
(グリーンピースのプラント・ジェネティクス・システム社特許に対する異議申し立て)
- 梶 正憲, 「新しい情報入手ツールサービス JDreamPetit, JDreamDaily」、情報管理、2004,
47(7), 500-502.
(JST の個人向け情報検索サービス)
- 殿崎 正明, 「日本の学術雑誌を育成して学術情報立国、知的財産立国を目指そう」,
オンライン検索、2004, 25(1/2), 1-4.
(Nature/Science を目指した雑誌を創刊すべきである)
- 宇野 嘉恵, 「Medical Subject Headings (MeSH) 2004 年版の変更点: 検索上の注意と最近の動向」,
オンライン検索、2004, 25(1/2), 5-13.
(MeSH の変更点の詳細)
- 加藤 砂織, 「オンラインジャーナル導入実績とその効果: 利用動向の分析から
(Impact of Online Journals On Medical School Libraries)」, オンライン検索、2004,
25(1/2), 14-23.
(東京女子医科大学の経験、冊子体の利用が減り、オンラインの利用が増えている、図書館の来館者も減少傾向にある)
- 遠山 美香子, 「高機能学術プラットフォーム: ISI Web of Knowledge による次世代研究支援環境の実現」,
オンライン検索、2004, 25(1/2), 38-47.
(Web of Knowledge の説明, Web of Science, CCC などとのリンク)
- 山田 奬, 「『Medical*Online』のワンストップ配信サービス」, オンライン検索、2004,
25(1/2), 48-52.
(医歯薬・医療分野の論文の PDF 提供)
- Shultz M, DeGroote SL., 「MEDLINE による SDI サービスの比較研究」,
オンライン検索、2004, 25(1/2), 53-54.
(PubMed Cubby, OVID, BioMail, PubCrawler, ScienceDirect, JADE)
- 根岸 正光, 「研究評価における文献の計量的評価の問題点と研究者の対応」,
薬学図書館、2004,
49(3), 176-182.
(インパクトファクター、NCRJ、日本型 SPARC)
- 松田 菜緒子, 「バイオ分野における大学発明の技術移転の現状と問題点」,
薬学図書館、2004,
49(3), 183-187.
(大学発明の権利化および利用の問題点)
- 秋元 浩, 「企業における知的財産戦略 - ライフサイエンス産業を中心として」,
薬学図書館、2004,
49(3), 188-194.
(武田薬品の経験)
- 安田 一郎, 「インターネットによる医薬品購入の現状と問題点」, 薬学図書館、2004,
49(3), 198-202.
(個人輸入とインターネット、健康食品に含まれる無承認無許可医薬品)
- 渡邊 伸一, 「医薬品の医療安全対策についての行政施策」, 薬学図書館、2004,
49(3), 203-206.
(構成労働省における取り組み)
- 加賀美 裕介, 「Pharmaceutical Substances オンライン版バージョン 2.0」,
薬学図書館、2004,
49(3), 207-211.
(Thieme が作成する医薬品データベース、化学物質 2,352 件、化学反応 8,200
件、化学構造 14,000 件)
- 末廣 恒夫, 「神奈川県資料室研究会と神奈川県立川崎図書館 - 新たな協力関係に向けて」、専門図書館,
2004, (206), 1-5.
(神資研と川崎図書館の協力関係)
- 武邑 光裕, 「デジタル・アーカイブにおける課題と展望」, 情報の科学と技術,
2004, 54(9), 440-446.
(次世代ミュージアム、リポジトリ、著作権、個人アーカイブ)
- 今野 篤, 「デジタル情報の長期的保存の政策 - アメリカと日本」, 情報の科学と技術,
2004, 54(9), 447-452.
(NDIPP, 国立国会図書館など)
- 中山 正樹, 「国のデジタル・アーカイブ・ポータルの構築 - 国立国会図書館『電子図書館中期計画
2004』の実施に向けて」, 情報の科学と技術,
2004, 54(9), 453-460.
(背景、骨子、考え方、方向、利用イメージ、仕様、考察)
- 栗山 正光, 「OAIS 参照モデルと保存メタデータ」, 情報の科学と技術,
2004, 54(9), 461-466.
(OAIS 参照モデル (Reference Model for an Open Archival Information System)
の詳細)
- 肥田 康, 「電子画像情報の利用と保存」, 情報の科学と技術,
2004, 54(9), 467-474.
(画像情報保存の諸問題、研究支援ソフト iPalletnexus)
- 尾城 孝一, 杉田 茂樹, 阿蘇品 治夫, 加藤 晃一, 「日本における学術機関リポジトリ構築の試み
- 千葉大学と国立情報学研究所の事例を中心として」, 情報の科学と技術,
2004, 54(9), 475-482.
(学術機関リポジトリとは, 海外の動向、千葉大学の例、国立情報学研究所の支援)
- 小川 裕子, 「東南アジアの特許情報を調べる」, 情報の科学と技術,
2004, 54(9), 483-487.
(中国、韓国、台湾)
- Johan F. Steenbakkers, 「オランダ国立図書館における電子ジャーナルのアーカイビング
(インタビュー)」、情報管理、2004,
47(6), 387-392.
(エルゼビアの雑誌の永久的保存をおこなっている)
- 玉田 俊平太, 児玉 文雄, 玄場 公規, 「重点 4 分野におけるサイエンスリンケージの計測
(上) サイエンスリンケージ - その意義と計測法」、情報管理、2004,
47(6), 393-400.
(特許に引用されている論文等の数を計測)
- 相澤 彰子, 「和英著者キーワードからの多言語類語辞書自動構築の試み」、情報管理、2004,
47(6), 401-409.
(学術情報センターが構築した学会発表データベースの和英著者キーワードから類語辞書を構築)
- Amy Brand, 高木 和子訳, 「CrossRef を介した学術文献リンキング」、情報管理、2004,
47(6), 410-418.
(CrossRef の概要、出版者へのインパクト、OpenURL との統合、仲介業者による適用、研究者への利益、Forward
linking, Multiple resolution, CrossRef Search など)
- 加藤 浩一郎, 「金沢工業大学大学院 <東京キャンパス> における文理融合型の知的財産教育について」、情報管理、2004,
47(6), 422-427.
(ウィニー開発者の逮捕とノルウェーの DeCSS 開発者の裁判との比較)
- 名和 小太郎, 「ウィニー; 論点あれこれ」、情報管理、2004,
47(6), 431-433.
(1995 年の British Medical Journal の「バイオメディカル・ジャーナルの死」論文に関する論争)
- Hao-Ren KE, 澤田 裕子訳, 「アジア諸国における情報サービスの利用 -
第 1 回: 台湾 CONCERT について」、情報管理、2004,
47(5), 305-314.
(設立、核心となるプログラム、資金と管理、その他のプログラム、など)
- 佐藤 勉, 林 賢紀, 「農林水産研究情報サービスへの取り組み - 検索システムの開発と
Web アーカイブ構築」、情報管理、2004,
47(5), 338-347.
(「検索システム農林一号」、Web アーカイブ、「農林水産研究関係インターネット資源への道」)
- 新井 規之, 「JST における特許化支援」、情報管理、2004,
47(5), 348-357.
(従来の大学の出願状況、今後の動向と課題、JST の各種支援制度、特許出願支援、大学の発明に特有な事項、など)
- 名和 小太郎, 「『ジャーナルの死』論争」、情報管理、2004,
47(5), 361-362.
(1995 年の British Medical Journal の「バイオメディカル・ジャーナルの死」論文に関する論争)
- 高木 和子, 「ライブラリアンのための著作権講義録」、情報管理、2004,
47(5), 363-369.
(著作権概観、新しい変化、図書館への影響、など)
- 田口 宣行, 「レファレンス解析・視覚化ツール RefViz」、情報管理、2004,
47(5), 370-373.
(医学関係の文献のキーワードの共出などを解析する)
- 土井 美和子、「ユーザビリティとインタフェース: ヒューマンインタフェースと
Web デザイン」、情報の科学と技術、2004,
54(8), 407-412.
(Web ユーザビリティ)
- 田中 秀樹、「使われるポータルサイト - ポータルソフトウェア開発を通じて」、情報の科学と技術、2004,
54(8), 413-420.
(ユーザが見やすいポータルサイトの作り方)
- 小川 裕子、「日米欧の特許情報を調べる」、情報の科学と技術、2004,
54(8), 425-432.
(全文検索、概念検索、権利情報、パテントファミリー、翻訳機能、など)
- 今野 浩, 「ソフトウェア特許論」、日経バイト、2004, (8), 69-74.
(ソフトウェア特許、ビジネスモデル特許は研究開発に役立つか)
- 岡 紀子、田中 章夫,「知験薬中間体ビジネスにおける新規用途調査法 -
知験薬中間体 DB の構築」、情報管理、2004,
47(4), 229-241.
(知験薬 2874 件と中間体 522,061 件を収録したデータベース)
- 土屋 俊,「COUNTER プロジェクト: 序論」、情報管理、2004,
47(4), 242-244.
(電子ジャーナルのアクセス統計のインパクト)
- ピーター・T・シェパード、高木 和子訳,「COUNTER プロジェクト - オンライン利用統計の国際基準の設定」、情報管理、2004,
47(4), 245-257.
(利用統計に関するイニシアチブ、COUNTER の起源、COUNTER 実施規範、リリース
2、COUNTER の組織、など)
- 加藤 多恵子,「デジタルライブラリーにおけるデジタルコレクション」、情報管理、2004,
47(4), 258-266.
(デジタルコレクションの種類、コレクション実例)
- 高橋 雄一郎、森川 清,「企業活動と知的財産制度 第 14 回: 職務発明訴訟の実務」、情報管理、2004,
47(4), 275-282.
(職務発明制度、「相当の対価」、訴訟の要件事実、立証活動、代理人の行動指針)
- ノーマ・ムスタファ, 「科学技術情報センターの運営: さまざまな課題」、情報管理、2004,
47(4), 283-285.
(マレーシアの MASTIC の活動)
- 名和 小太郎, 「コモンズの悲劇、反コモンズの悲劇」、情報管理、2004,
47(4), 286-288.
(生物医学的研究における特許の強化が研究を阻害する可能性、MPEG2、著作権の細分化)
- 大場 高志, 杉田 茂樹, 「国立情報学研究所のメタデータ・データベース共同構築事業について」、大学図書館研究、2004,
(70), 25-30.
(論文、実験データ、研究者情報、シラバス、図書館情報、DB、大学広報、その他のメタデータをデータベースに)
- 近内 尤已, 「日本国公私立大学コンソーシアム連合 (JCOLC - Japan Coalition
of Library Consortia) の発展に向けて」、大学図書館研究、2004, (70), 63-69.
(2002 年の JCOLC 誕生までの経緯とその後の活動)
- 今川 裕子、「2004 年外国雑誌の契約を終えて」、薬学図書館、2004,
49(2), 71-74.
(明治薬科大学図書館の経験)
- 長縄 友子、「2004 年外国雑誌契約を終えて - 企業資料室における洋雑誌購読」、薬学図書館、2004,
49(2), 75-79.
(味の素 (株) ライフサイエンス研究所図書室の経験)
- 母良田 功、「外国雑誌価格高騰への対応 - サイエンス・ダイレクト・トランザクション
(Pay Per View) の導入」、薬学図書館、2004,
49(2), 80-83.
(昭和薬科大学図書館の経験)
- 大熊 高明、「電子ジャーナルの普及と最近の動向」、薬学図書館、2004,
49(2), 89-95.
(購読形態の多様化、コンソーシアム契約、アーカイブ、書籍コンテンツ、Pay
per View)
- 設楽 真理子、「次世代リンクシステム - Ovid LinkSolver」、薬学図書館、2004,
49(2), 89-95.
(Ovid LinkSolver の紹介)
- 中野 敦子、「世界の WEB 版医薬品集」、薬学図書館、49(2),
120-140, 2004.
(医薬品情報提供 HP、PDR, electronic Medicine Compendium, British National
Formulary, ROTE LISTE, BIAM, Vidal Pro, Arzneimittel-Kompendium, など)
- 母良田 功、「日本薬学図書館協議会電子ジャーナル・コンソーシアムの取組み
- 雑誌問題検討委員会報告」、薬学図書館、2004,
49(2), 141-145.
(2004 年契約の詳細)
- 藤生 守男、「医薬品研究所におけるナレッジシェアシステム: Virtual Library」、薬学図書館、2004,
49(2), 146-152.
(中外製薬の EndNote を用いたネットワークシステム)
- 長谷川 大輔、「電子ジャーナル管理システム E-J Solution」、薬学図書館、2004,
49(2), 146-152.
(E-J Solution の紹介)
- 北 克一、「主題情報の検索: 総論」、情報の科学と技術、2004,
54(7), 334-340.
(主題の表現と手法、主題の外的圧縮、検索結果の評価とブール演算、マルチメディア文献の検索)
- 大場 利康、川鍋 道子、「図書における主題検索 - NDL-OPAC での検索と国立国会図書館の取組み」、情報の科学と技術、2004,
54(7), 341-347.
(NDC 検索、件名検索、NDLSH 改訂作業)
- 竹内 貴広、「雑誌論文における主題情報の検索: 化学・医学分野を中心に」、情報の科学と技術、2004,
54(7), 348-354.
(医中誌 Web, JMEPlus, PubMed などのタイトル、抄録、統制語の検討)
- 高橋 昭公、「特許情報における主題情報の検索: 概念検索とその限界」、情報の科学と技術、2004,
54(7), 355-362.
(概念検索の概要、NRI, PATOLIS-IV, ATMS の比較)
- 北島 由紀子、「医薬品情報の Bookmark」、情報の科学と技術、2004,
54(7), 371-376.
(医薬品情報提供サイト、医薬品の承認申請情報、添付文書・製品情報)
- 鈴木 茂, 「知的財産と専門図書館」、専門図書館,
2004, (205), 1-8.
(知的財産権の概要)
- 山本 順一, 「科学技術文献、学術情報と著作権 - 専門図書館の視点から」、専門図書館,
2004, (205), 9-16.
(アメリカ連邦著作権法、科学技術基本法、著作権法施行令 1 条の 3 第 6 号、電子ジャーナルなど)
- 前園 主計, 「著作権法附則 4 条の二の廃止と専門図書館」、専門図書館,
2004, (205), 17-19.
(貸与権特例の廃止について)
- 野澤 隆, 「ごぞんじですか? ビジネス著作権検定」、専門図書館,
2004, (205), 27-31.
(貸与権特例の廃止について)
- 田中 満恵、「外国雑誌におけるコア雑誌選定の経緯」、医学図書館、2004,
51(2), 132-136.
(東京慈恵会医科大学における経験、アンケート、図書委員会)
- 北川 正路、「プリント版から電子ジャーナルへ切り替える外国雑誌タイトルの選定:
コア雑誌タイトルを考慮した検討」、医学図書館、2004,
51(2), 137-140.
(東京慈恵会医科大学における電子ジャーナルの利用状況と切り替えの実施)
- 宇野 彰男、伊藤 茂樹、「電子ジャーナルの相互貸借利用: アンケート結果に見るその問題点」、医学図書館、2004,
51(2), 147-151.
(日本医学図書館協会関東地区会 47 館へのアンケート)
- 長塚 隆,「学術データ・データベースと知的財産権」、情報知識学会誌、2004,
14(2), 5-8.
(パブリックドメインとしての学術データ・データベース、生物多様性データ・データベースなど)
- 村橋 俊一,「わが国欧文誌の現状と問題点」、情報管理、2004,
47(3), 149-154.
(国内の欧文誌の現状、論文の海外流出、電子ジャーナルの課題と強化、助成と投資など)
- 松山 裕二,「大学の論文発表:電子ジャーナルを使用した計量書誌的考察」、情報管理、2004,
47(3), 164-174.
(論文数と雑誌数、雑誌集中度、共著、論文と特許、被引用など)
- 岡 紀子, 田中 章夫,「Chemical Abstracts 文献を利用した有望中間体の探索方法」、情報管理、2004,
47(3), 175-181.
(Pioneer, 明日の新薬、Cipsline, Pharmastructures などの治験薬データベースで化合物を抽出、CA
で合成中間体を抽出 - 治験薬 2874 件に対し、12,490 件の中間体候補)
- 鎌田 真理雄,「企業活動と知的財産制度 第 13 回: デジタルコンテンツの保護制度の現状」、情報管理、2004,
47(2), 189-198.
(著作権法、不正競争防止法、プロバイダー責任法、不正アクセス禁止法、および今後の課題など)
- 名和 小太郎,「政府主導のピア・レビュー」、情報管理、2004,
47(2), 202-203.
(米国行政管理予算局 (OMB) の「規制科学におけるピア・レビュー標準案」に対する、全米科学アカデミー、米国科学振興協会、米国科学者連合、米国生態学会などの意見)
- 高木 和子,「OhioLINK 最近の活動状況と今後の計画」、情報管理、2004,
47(2), 204-211.
(OhioLINK の歴史と現在の活動、財政)
- Gary Stix、「特許が技術革新を妨げるという皮肉」、日経サイエンス、2004(8),
135-137.
(Adam B. Jaffe, Josh Lerner, "Innovations and Its Discontents",
連邦巡回控訴裁判所と特許手数料による運営が特許権利者の保護を進め、技術革新を妨害している)("Staking
Claims: Patents on Ice", Scientific
American, 2004(6), 46.)
- Gary Stix、「南極の生物資源を特許化する - 知的所有権の最後のフロンティアに熱いまなざし」、日経サイエンス、2004(7),
108-109.
(スペインで南極赤潮殺藻細菌、ドイツで緑藻抽出物の特許)("Staking Claims:
Patents on Ice", Scientific
American, 2004(5), 48.)
- Gary Stix、「先行技術なんか気にしない - コスタリカ流『特許権行使』がビッグビジネスを揺さぶる」、日経サイエンス、2004(6),
99-101.
(キャノピーツアーの特許が成立し、業界がパニックになっている)("Staking
Claims: Patent Enforcement", Scientific
American, 2004(4), 42.)
- Gary Stix、「大学よお前もか - 特許をめぐるエゴは、もはや企業だけのものではない」、日経サイエンス、2004(5),
137-135.
(コロンビア大学は期限が切れたバイオ特許を延長しようとして新しい特許を取得した)("Staking
Claims: Working the System II", Scientific
American, 2004(3), 41.)
- 岡 紀子、田中 章夫、「合成反応設計システムを利用した有望中間体の探索方法」、情報管理、2004,
47(2), 73-81.
(合成デザインシステム SYNSUP を利用して医薬の合成中間体として有望なものを抽出)
- 千原 秀昭、「化学情報システムの変遷」、情報管理、2004,
47(2), 82-95.
(化学情報の歴史)
- 原田 郁子、「JST
収集・収録誌と海外主要データベース収録誌との比較」、情報管理、2004,
47(2), 96-101.
(BIOSIS, MEDLINE, COMPENDEX, INSPEC, PASCAL, SciSearch との比較)
- 豊田 正雄、「企業活動と知的財産制度 第 12 回: ソフトウエア・プログラムの保護制度の現状」、情報管理、2004,
47(2), 108-116.
(ソフトウェア特許、ビジネスモデル特許など)
- Uwe Rosemann、熊谷 玲美 訳,「vascoda - 学術ポータル」、情報管理、2004,
47(2), 102-107.
(ドイツの科学技術ポータル)
- 中西 博、「科学技術情報の虚実」、情報管理、2004,
47(2), 117-119.
(ベル研究所の不正論文について)
- 名和 小太郎、「電波はだれのものか」、情報管理、2004,
47(2), 120-121.
(マルコーニの無線通信の発明から現代の電波の争奪まで)
- 上野 裕之、「官報情報検索サービスについて」、情報管理、2004,
47(2), 124-126.
(独立行政法人国立印刷局のサービス)
- 倉田 敬子、「科学技術情報流通の仕組: 学術雑誌の役割」、情報の科学と技術、2004,
54(6), 276-281.
(学術雑誌の科学研究における役割、電子ジャーナル、フリーアクセス、など)
- 松木 秀彰、「科学研究費補助金の『研究成果報告書』ができるまで」、情報の科学と技術、2004,
54(6), 282-288.
(研究成果報告書は国立国会図書館に納本される)
- 永田 龍二, 浅見 真理, 高階 恵美子, 中谷 比呂樹, 「厚生労働科学研究費補助金の取り組みについて:
その意義と成果の普及」、情報の科学と技術、2004,
54(6), 289-293.
(厚生労働科学研究成果データベースで公開される)
- 板橋 良則, 三島 順子, 黒沢 努, 「科学技術振興機構における基礎研究事業の成果公表と流通
- 科学技術振興機構中期計画を中心として」、情報の科学と技術、2004,
54(6), 294-302.
(研究成果は J-STORE, J-STAGE で公開される)
- 大竹 晴日虎, 「政府補助金等による研究開発情報の収集とサービス - 政府資料等普及調査会の経験から」、情報の科学と技術、2004,
54(6), 303-309.
(「政府資料データベース」を作成)
- 調 麻佐志, 「学術論文データベースを利用した研究評価 - bibliometrics
指標の限界と可能性」、情報の科学と技術、2004,
54(6), 317-323.
(インパクト・ファクター、被引用数などの効果と限界)
- 菊池 健司, 「統計情報」、情報の科学と技術、2004,
54(6), 324-327.
(官庁統計、市場情報など)
- 小川 裕子, 「特許検索に使われるデータベースとシステム」、情報の科学と技術、2004,
54(5), 214-223.
(中国特許庁、台湾特許庁、esp@cenet, epoline, PATOLIS-IV)
- 武藤 晃, 「データベースを深く知る, 上達の決め手は洞察力とコスト意識」、情報の科学と技術、2004,
54(5), 225-228.
(特許検索のノウハウ, DVD 公報のエラーの影響、日本と米国の IPC の違いなど)
- 鈴木 利之, 「特許法を知る」、情報の科学と技術、2004,
54(5), 229-234.
(特許公報の言葉の意味、特許法での特許公報、特許権はいつ切れる)
- 長澤 洋, 「検索に必要な主題知識を補う」、情報の科学と技術、2004,
54(5), 235-239.
(サーチャーへのアンケート調査の結果より)
- 石田 由利子, 「エンドユーザー教育と検索システムの選択」、情報の科学と技術、2004,
54(5), 240-247.
(エンドユーザー教育のカリキュラム)
- 桐山 勉, 「データの加工と解析」、情報の科学と技術、2004,
54(5), 248-253.
(パテントリスト・マップ、加工のためのデータ収集・取込・加工、ソフトやシステムの比較)
- 越智 泰子 「特許検索に関する情報交換がてきる団体」、情報の科学と技術、2004,
54(5), 254-259.
(各種団体の紹介)
- 菊池 健司 「財務情報 (有価証券報告書・売上情報)」、情報の科学と技術、2004,
54(5), 260-263.
(上場企業、未上場会社の財務データ、海外の企業情報)
- 照井 啓子、加藤 弘子、中村 容子、「研究所技報の電子ジャーナル化とその効 果
- 『豊田中央研究所 R&D レビュー』の事例紹介」、情報管理、2004,
47(1), 8-14.
(QuarkXPress で PDF を作成し Web 公開、別刷り作成、バックナンバーの電子化)
- 岡本 和彦、「宇部興産 (株) におけるエンドユーザ教育 - 研究開発本部における『情報検索アドバイザー制度』」、情報管理、2004,
47(1), 15-19.
(NRI サイバーパテント、PATENT-NET, PATOLIS, PATENT Web, New JOIS, ScienceDirect,
STN/STN Easy, SciFinder, CrossFire のエンドユーザ教育)
- 辻丸 光一郎、「企業活動と知的財産制度 第 11 回: 遺伝子情報保護の現状と課題」、情報管理、2004,
47(1), 20-28.
(遺伝子情報の特許法による保護、バイオインフォマティックスに関する判例など)
- 千原 秀昭、「STN: つぎの 20 年にむかって」、情報管理、2004,
47(1), 29-32.
(STN の歴史、現状)
- 熊谷 玲美、「オープンアクセス出版」、情報管理、2004,
47(1), 33-37.
(PLos, Sabo 法案、Budapest Open Access Initiative など)
- 名和 小太郎、「シャーマン宣言」、情報管理、2004,
47(1), 42-44.
(「先住民の智恵・科学および工業所有権」についての宣言)
- 高木 和子、「悩み多き 2003 年の図書館界 10 大ニュース」、情報管理、2004,
47(1), 45-52.
(児童インターネット保護法、米国愛国者法、RoweCom、イラク、クラーク・アトランタ大学の図書館情報学部閉鎖、SARS、図書館サービス法、カリフォルニア州の苦難、フロリダ州立図書館)
- 岸田 和明、「電子的な図書館サービスの評価への取り組みとその課題」、情報の科学と技術、2004,
54(4), 162-167.
(ISO/TR 20983, COUNTER など)
- 加藤 信哉、「電子情報資源の利用統計 - COUNTER プロジェクトと実務コードを中心に」、情報の科学と技術、2004,
54(4), 168-175.
(COUNTER (Counting OnlineUsage of NeTworked Electronic Resources) プロジェクトの目的とその実務コード
(Code of Practice) の詳細)
- 蒲生 英博、「大学図書館における評価指標報告書 (Version 0) の作成とその後の動向
- 特に電子図書館サービス関係評価指標について」、情報の科学と技術、2004,
54(4), 183-189.
(電子図書、電子ジャーナルに関する評価指標)
- 渡辺 正彦、「医学文献の全文検索」、情報の科学と技術、2004,
54(4), 198-202.
(HighWire, Synergy, Interscience, Karger, Nature.com, Cell Press, ScienceDirect,
J-Stage, Journal@Ovid, Ingenta select, Scirus の比較)
- 吉原 賢二、 「ニッポニウム発見 - 小川正孝・英次郎父子 通り過ぎたセレンディピティー」、現代化学、2004(5),
37-41.
(小川正孝が発見したニッポニウムは原子番号 43 と考えていたが、実は原子番号
75 のレニウムであった)
- 鬼木 裕之進、 「安衛法の適用にどう対応するか - 化学実験室の有害化学物質対策」、化学と工業、2004,
57(4), 419-422.
(国立大学が独立行政法人となるにあたり、労働安全衛生法が適用されるので、その規制のあらましについて述べた)
- 南 亮一、「著作権をめぐる最近の動向」、薬学図書館、2004,
49(1), 1-8.
(文献複写関係の著作権法改正と改正検討動向について)
- 泉 浩三、「学内向け雑誌ポータルサイトの構築」、薬学図書館、2004,
49(1), 9-13.
(東京薬科大学の経験)
- 武田 浩一、浦本 直彦、松澤 裕史、長野 徹、村上 明子、竹内 広宣、「大規模生物医学文献データベースのテキストマイニング・ツール」、薬学図書館、2004,
49(1), 29-33.
(日本 IBM の MedTAKMI による MEDLINE のテキストマイニング)
- 保田 明夫、須永 恭子、「テキスト型データ解析ソフトウェア WordMiner」、薬学図書館、2004,
49(1), 34-41.
(地域看護学の学生総評の分析)
- 藤垣 裕子、「ジャーナル共同体におけるレビュー誌の役割」、情報の科学と技術、2004,
54(3), 102-108.
(レビュー誌の役割として、引用とレビューを考える)
- 棚橋 佳子、宮入 暢子、「引用動向からみたレビュー誌およびレビュー論文」、情報の科学と技術、2004,
54(3), 109-114.
(Journal Citation Reports の分析によれば、生化学、分子生物学、薬理・薬学にはレビュー誌が多く、レビュー論文の出版数ものびている。)
- 石川 正、羽原 正、大島 健志、「電子ジャーナル導入による外国雑誌の利用動向の変化
(日本原子力研究所の場合)」、情報の科学と技術、2004,
54(3), 126-132.
(Journal of Nuclear Materials., Phsical Review Letters, Nature について見ると、貸出と文献複写件数が大幅に減少し、ダウンロード件数が非常に増加した)
- 松本 優、「わが国産業界におけるナレッジ・マネジメント (KM) の実例
- (株) リコーの販売部門におけるナレッジ・マネジメントの実践事例」、情報管理、2004,
46(12), 804-815.
(「おじさん通信」)
- 長塚 隆、「企業活動と知的財産制度 第 10 回: データベースの保護制度の現状と課題」、情報管理、2004,
46(12), 816-827.
(著作権法、EC データベース指令など)
- 石黒 武彦、「総合科学雑誌における不正行為論文の逐次刊行とその撤回および背景」、情報管理、2004,
46(12), 828-834.
(ベル研究所 Shoen 論文事件)
- 名和 小太郎、「情報ビジネス地図・再考 (下)」、情報管理、2004,
46(12), 843-845.
(コンテンツ、コンテナー、サービス、プロダクト)
- 阿部 博之、「わが国の知的財産戦略と科学研究について」、情報管理、2004,
46(11), 711-716.
(大学における知的財産の活用と保護)
- 渡邉 知子、「企業活動と知的財産制度 第 9 回: 意匠制度の現状と課題」、情報管理、2004,
46(11), 752-761.
(意匠制度の概要)
- 名和 小太郎、「情報ビジネス地図・再考 (上)」、情報管理、2004,
46(11), 768-769.
(コンテンツ、コンテナー、サービス、プロダクト)
- 日本学術会議 (第 18 期) 学術と社会常置委員会、 「科学における不正行為とその防止」、化学と工業、2004,
57(2), 144-146.
(九州大学)
- 小幡 明彦、瀬川 智子、伊藤 誠記、小林 正、「Web
ユーザビリティの改善 - 情報処理学会の Web サイトを題材にして」、情報処理,
2004, 45(1), 170-176.
(シナリオウォークスルー法による評価と改善)
- Gary Stix、「特許の延命は許されるか」、日経サイエンス、2004(4),
123-125.
(Genentech 社と Celltech 社の共謀でモノクローナル抗体の特許が 12 年も延長されようとしていると、MedImmune
社が訴えた)("Staking Claims: Kick Me, Myself and I ", Scientific
American, 2004(2), 32.)
- 国立情報学研究所 SPARC/JAPAN 推進室、 「SPARC/JAPAN 事業について」、大学図書館研究、2004(2),
42-46.
(SPARC/JAPAN の経緯と現状)
- 福島 俊一、「検索エンジンの仕組みと技術の発展」、情報の科学と技術、2004,
54(2), 66-71.
(人手による収集、クローラ、リンク解析)
- 住 太陽、「検索エンジン業界勢力地図」、情報の科学と技術、2004,
54(2), 72-77.
(提携と買収)
- 兼宗 進、「検索エンジンの検索アルゴリズム」、情報の科学と技術、2004,
54(2), 78-83.
(収集、全文検索、ランキング)
- 山名 早人、「検索エンジンのアーキテクチャ」、情報の科学と技術、2004,
54(2), 84-89.
(収集、インデキシング、ハードウェア)
- 関 裕司、「利用者側から見た Google の特徴と使用方法」、情報の科学と技術、2004,
54(2), 90-94.
(キーワードの取り扱い、キーワードの組合せ、ブーリアンとオプションコマンド)
- 伊藤 義人、 「変革の時代に於ける図書館経営戦略 - 存在感ある図書館を目指して」、第
19 回大学図書館研究集会記録 (2002. 9. 19 早稲田大学、東京)、2003. 1. 31,
pp. 9-25.
(電子ジャーナルコンソーシアム、図書館の戦略的連携、など)
- 村田 徳治、 「ごみ固形燃料 RDF と事故」、現代化学、2004(2),
42-46.
(RDF はエネルギー収支が悪く、燃料として不適当である)
- 山本 明夫、 「化学の夜明け (1) - ヨーロッパと日本」、現代化学、2004(1),
14-18.
(蘭学と化学)
- 山本 明夫、 「化学の夜明け (2) - 革命の時代」、現代化学、2004(2),
49-55.
(シェーレ、プリーストリ、ラボアジェ)
- 山本 明夫、 「化学の夜明け (3) - 19 世紀前半の化学者たち」、現代化学、2004(3),
38-46.
(ドルトン、ベルセリウス、リービッヒ、ウェーラー)
- 山本 明夫、 「化学の夜明け (4) - 日は昇る」、現代化学、2004(4),
16-23.
(メンデレーエフ)
- 秋元 浩、「知的財産情報の活用 - ライフサイエンス業界を中心として」、情報管理、2004,
46(10), 642-646.
(最近の権利侵害判例、知財立国に向けての課題、医療行為の特許化問題、裁定実施権など)
- 岩岡 保彦、「わが国産業界におけるナレッジ・マネジメント - 三菱化学の
R&TD におけるナレッジ・マネジメントへの取り組み」、情報管理、2004,
46(10), 656-662.
(eNOTE, Technology Suply Chain, Technology Map, NLP 自然言語処理、Know
What, Know Who)
- 青山 紘一、「企業活動と知的財産制度 第 8 回: 不正競争防止法による知的財産権侵害の規制の現状」、情報管理、2004,
46(10), 672-680.
(不正競争防止法の概要、不正競争の実例、対抗手段)
- 名和 小太郎、「著作権管理: 3 つのモデル」、情報管理、2004,
46(10), 687-688.
(伝統的著作権保持者、コンテンツ事業者、ユーザ群、がそれぞれ主張する著作権管理方法、コピーマート、超流通システム、クリエイティブ・コモンズ)
- 赤壁 幸江、「中国特許情報調査」、情報の科学と技術、2004,
54(1), 43-49.
(中国知的財産局データベース、他のデータベースとの比較)
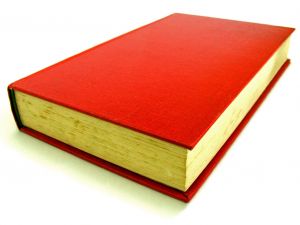 根岸正光, Ann
S.Okerson, 伊藤義人, Raym Crow, 佐藤寛子, James Testa, 安達淳, 土屋俊,
早瀬均. 「電子図書館と電子ジャーナル : 学術コミュニケーションはどう変わるか」.
丸善. 2004, 157p.
根岸正光, Ann
S.Okerson, 伊藤義人, Raym Crow, 佐藤寛子, James Testa, 安達淳, 土屋俊,
早瀬均. 「電子図書館と電子ジャーナル : 学術コミュニケーションはどう変わるか」.
丸善. 2004, 157p.
- 電子図書館と電子ジャーナル−最近の動向と今後の課題
- ディジタル・コレクション−小惑星、ムーアの法則、スター・アライアンス
- 電子図書館とデンシジャーナル−新しい挑戦
- SPARC2003−機関レポジトリーとオープン・アクセス
- 化学系情報のディジタル化と研究の発展
- ISIのジャーナルの選定プロセス5年後の学術コミュニケーション
-1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, Latest