化学情報、薬学情報、データベースに関する文献
2001 年 (国内)
-1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, Latest
- 特許庁総務部技術調査課技術動向班、「ノーペル賞と特許 (2001 年版)」、2001.
10, <http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search.cgi?query=%83m%81%5B%83x%83%8B%8F%DC&lang=jp&root=short>
(2003. 7)
- 江口 愛子、「浜松医科大学における電子ジャーナルの導入」、医学図書館、48(4),
369-372, 2001.
(IDEAL, ScienceDirect, LINK, Blackwell, Wiley, LWW, ProQuest, EBSCOmed
など)
- 藏野 由美子、瀬川 紀代美、飯塚 亜子、近藤 真智子、「東京大学附属図書館における『電子ジャーナル導入実験について」、大学図書館研究、63,
27-44, 2001.
(導入の経過と利用実績)
- 船渡川 清、「引用リンクを基盤にした高機能学術文献情報プラットフォームの形成
- 国立情報学研究所 (学術情報センター) 情報サービス高度化に向けた一戦略」、大学図書館研究、61,
1-7, 2001.
(NACSIS-CAT, NACSIS-ILL, NACSIS-IR, NACSIS-ELS, NACSIS-OLJ などの結合)
- 船渡川 清、「国立情報学研究所(学術情報センター)電子図書館サービスにおける著作権処理モデル」、大学図書館研究、60,
58-62, 2001.
(NACSIS-ELS における電子化の許諾、利用許諾の手続き、利用者による著作物利用段階での著作権処理、料金徴収の仕組み)
- ビル・ステューダー、遠山 美香子抄訳、「オハイオリンク・コンソーシアムでの事例:
共同購入ライセンス、リソースシェアリング、及びフルテキストと 2 次資料データベースの統合」、大学図書館研究、61,
54-64, 2001.
(OhioLINK の活動)
- 吉田 幸苗、牧村 正史、大埜 浩一、「電子ジャーナル・コンソーシアムの形成
- JIOC/NU の現状と課題」、大学図書館研究、61,
65-67, 2001.
(国立大学図書館協議会の活動)
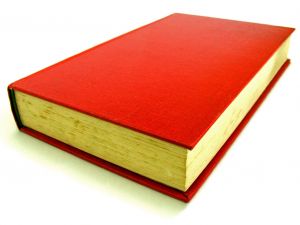 根岸正光, 山崎茂明編著.
「研究評価 : 研究者・研究機関・大学におけるガイドライン」. 丸善. 2001,
204p.
根岸正光, 山崎茂明編著.
「研究評価 : 研究者・研究機関・大学におけるガイドライン」. 丸善. 2001,
204p.
- 研究評価とビブリオメトリックス
- 研究評価指標としての論文生産数
- 論文生産数の国際比較
- 指標としてのインパクト・ファクター
- わが国の大学の論文生産と引用数
- わが国の学会誌の引用索引データベース
- 研究評価のための学術データベース
- 研究評価のためのレフェリー・システム
- 江口 愛子、「浜松医科大学における電子ジャーナルの導入」、医学図書館、48(4),
369-372, 2001.
(IDEAL, ScienceDirect, LINK, Blackwell, Wiley, LWW, ProQuest, EBSCOmed
など)
- シュレンバーガー, デイビッド E.、高木 和子訳、 「新しい科学出版システムへの指針」、情報管理、44(9),
599-608, 2001.
(雑誌価格の急騰に伴う問題点と、その解決策について、特に 2000. 3 に開催された会議の提言について)
- 丹羽 由一、 「アジアの IT 人材育成 - 中国: 国家戦略による大学の活用と起業支援」、情報管理、44(9),
609-613, 2001.
(北京大学や精華大学の校弁企業について)
- 出水 晶、 「東レ (株) の図書情報管理 - 電子ジャーナルの導入に際して」、情報管理、44(9),
614-621, 2001.
(電子ジャーナル導入の経験)
- 松村 多美子、 「デジタル・アーカイビング
- 電子ジャーナルを中心に」、情報管理、44(9),
622-628, 2001.
(OCLC/RLG プロジェクト、Elsevier Science、アーカイブ・レポジトリなど)
- 伊藤 民雄、 「ウェブ情報の検索: 情報源の効果的な探索」、情報管理、44(9),
629-640, 2001.
(検索エンジンについて、サブジェクト・ゲートウェイ、デジタル・レファレンス、など)
- 山崎 茂明、「科学の不正行為への生態学的アプローチ」、情報の科学と技術、51(12),
602-608, 2001.
(頻度の解析、オーサーシップ、重複発表、その他)
- 横山 輝雄、「科科学技術における倫理問題」、情報の科学と技術、51(12),
609-613, 2001.
(倫理的な視点)
- 佐治 重豊、「医学雑誌の科学情報倫理 - 邦文誌編集委員の立場から」、情報の科学と技術、51(12),
614-618, 2001.
(医学雑誌の基本倫理、編集者の倫理、投稿規定など)
- 中村 宗知、「特許情報及び特許における倫理」、情報の科学と技術、51(12),
619-623, 2001.
(特許法の規定、明細書の書き方、生命倫理など)
- 山本 順一、「人文社会系研究者の生態と研究上の倫理」、情報の科学と技術、51(12),
624-629, 2001.
(理科系研究者との違い、独創性について)
- 佐々木宏子、「新・世界の医薬品集 (3)、ヨーロッパ - その 2」、薬学図書館、46(4),
360-385, 2001.
(スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガルの医薬品集)
- 佐藤 憲一、「薬学生に求められる情報リテラシー」、薬学図書館、46(4),
303-306, 2001.
(どんな情報リテラシーが必要か)
- 高橋 克明、「薬横浜市立大学学術情報センターにおける情報リテラシー教育への取り組み」、薬学図書館、46(4),
307-311, 2001.
(学内、学外へのガイダンスなど)
- 平 紀子、「北海道医療大学総合図書館における利用者教育」、薬学図書館、46(4),
312-317, 2001.
(医薬品情報学、情報科学などのカリキュラム)
- 和田 義親、「明治薬科大学における情報リテラシー教育」、薬学図書館、46(4),
318-322, 2001.
(情報処理演習、情報科学概論)
- 野添 篤毅、「PubMed - その構造と検索機能」、薬学図書館、46(4), 323-332,
2001.
(Feature Bar, MeSH Browser, Clincal Queries、全文リンクなど)
- 金子 康樹、「CC Connect の新機能について: 全文検索エンジン eSearch
と Web コンテンツ」、薬学図書館、46(4), 386-389, 2001.
(最近の機能強化について)
- Warren Holder、小山内 正明訳、「トロント大学における電子ジャーナル利用の実態」、薬学図書館、46(4),
394-398, 2001.
(Elsevier Science の Science Server など)
- グリベル, レス、内田 尚子訳、 「E-BioSci とゲノミックス革命後の生物情報管理の課題」、情報管理、44(8),
537-550, 2001.
(ゲノム情報の現状と、E-BioSci の構想)
- 末廣 恒夫、 「資生堂リサーチセンター図書室の運営と課題」、情報管理、44(8),
564-568, 2001.
(電子ジャーナル、データベースなどの利用)
- 山本 和雄、「電子ジャーナル等の電子出版物を、公的機関に導入する際に考えなければならない契約上の問題点」、情報の科学と技術、51(11),
556-564, 2001.
(会計制度、契約形態、法令、運用、著作権など)
- 五味 俊和、「出版物再販制度存廃の攻防」、情報の科学と技術、51(11),
565-572, 2001.
(再販制度見直し問題の経過と決着)
- 南 亮一、「図書館資料の貸出しと複写の法的裏付けに着いて」、情報の科学と技術、51(11),
573-578, 2001.
(物品管理、著作権法など)
- 三浦 勲、「外国文献複写と著作権」、情報の科学と技術、51(11),
579-584, 2001.
(CCC、学術著作権協会、著作権等管理事業法などについて)
- 米澤 誠、「NACSIS-CAT の現状と総合目録データベース統計」、医学図書館、48(3),
267-273, 2001.
(言語別、出版国別統計)
- 野添 篤毅、「EBM を支援する米国医学図書館の活動: 専門家から消費者へ」、医学図書館、48(3),
20-299, 2001.
(MEDLINE Plus, オンライン・レファレンス・サービスなど)
- 隅蔵 康一、 「研究者の知的財産とは - 特許権や研究サンプルは誰のものか」、現代化学、2001(11),
62-63.
(青色発光ダイオードや遺伝子スパイ事件に関連して)
- 古谷 実、 「電子文献の参照をどう書くか - SIST 02補遺の公刊にあたって」、情報管理、44(7),
470-477, 2001.
(インターネットのアドレスや電子メールなど、電子文献を参照する場合の記述の基準について)
- 坂内 悟, 土屋 江里, 絹川 雅祥, 河村 昌哉, 斉藤 隆行, 水野 充, 浜中
寿, 堀江 隆、 「分散型デジタル・コンテンツ統合システムの構築」、情報管理、44(7),
478-487, 2001.
(インターネット上の科学技術情報を統合的に検索するシステム、2001. 7 から試験運用)
- 長塚 隆、 「インターネットでの電子出版 - 電子本から電子ジャーナルまで」、情報管理、44(7),
503-513, 2001.
(電子本、電子ジャーナル)
- 鈴木 理、岡本 治正、「ノーベル化学賞受賞者 A. クルーグ博士に聞く」、現代化学、2001(9),
26-34.
(ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所における tRNA の研究と競争について)
- 窪田 輝蔵、 「現代の学術雑誌: その変遷と課題」、情報管理、44(6),
391-401, 2001.
(論文数の増大に対する Nature, Biochimica et Biophysica Acta の対応、レフェリー制度、電子ジャーナル、出版社の変貌、図書館の変化、わが国の問題、など)
- 吉村 忠与志、 「情報インフラによる教育改善」、化学と工業、54(9), 1076,
2001.
(情報インフラの進歩にあわせた教材開発)
- 木村 優、 「学会誌のレベルアップのために」、化学と工業、54(9), 1076-1077,
2001.
(Bull. Chem. Soc. Jpn の危機について)
- 関 祐司、「ポータルからポータルへ: 分野別専門サイトの厳選紹介」、情報の科学と技術、51(9),
477-483, 2001.
(All About Japan, Ask Jeeves, SOYOUWANNA.COM, everyrule.com, Top9.com,
Yakeo, e-Gov, ザ・議員、ComTrack, 東洋経済新聞社、EconDash, b-clip, ACADEMIC
RESOURCE GUIDE, ARIADNE, 青空文庫、専門書の杜、インターネット古書案内、その他)
- 呑海 沙織、「英国における学術情報資源提供システム」、情報の科学と技術、51(9),
484-494, 2001.
(HEFC, JISC, CHEST, BIDS, NESLI, ATHENS などの紹介)
- 野田 利章、「医学薬学データベースの比較」、薬学図書館、46(3), 215-221,
2001.
(MEDLINE, EMBASE, Derwent Drug File, Chemical Abstracts の比較)
- 阪田 久美子、「医薬品と情報公開: 医薬品情報学教育の立場から」、薬学図書館、46(3),
234-239, 2001.
(医薬品情報学のカリキュラムの変遷)
- 松田 真美、「医学中央雑誌インターネットサービスについて (4) 医中誌
WEB のこれから」、薬学図書館、46(3), 259-263, 2001.
(データベースの改善、インタフェースの改善、リンクについて)
- 南 亮一、「電子時代の著作権 Q&A (5)」、薬学図書館、46(3)),
264-2733, 2001.
(電子ジャーナルの著作権処理など)
- Mark McBride、「Pharma-Transfer: 必要不可欠な薬学情報」、薬学図書館、46(3),
281-282, 2001.
(バイオ・薬学分野の未発表の研究開発情報)
- 伊藤 眞人、 「遠隔教育、仮想化学教育で化学教育は変わるか」、化学と工業、54(8),
875-877, 2001.
(コンピュータによる教育支援)
- 生尾 光、 「100 年後の化学実験室 - 学生実験は存続できるのか」、化学と工業、54(8),
878-880, 2001.
(実験のスモールスケール化とバーチャル実験)
- 田丸 謙二、 「21 世紀の理科教育」、化学と工業、54(8), 885-888, 2001.
(理科教育の問題点)
- 村上 泰子、「図書館界とメタデータ: 米国議会図書館の戦略を中心に」、情報の科学と技術、51(8),
402-408, 2001.
(メタデータに関する各種プロジェクトの紹介)
- 鹿島 みづき、「CORC プロジェクトに参加して」、情報の科学と技術、51(8),
409-417, 2001.
(OCLC の CORC プロジェクトに参加し、目録作成をおこなった)
- 末広 幸治、山口 隆、 「特許戦争の動向と制度改革 - 新聞記事から」、情報管理、44(5),
319, 2001.
(「創作性」のあるなしにかかわらず,一定の投資がなされているデータベースを保護する「新たな権利(sui
generis right)」を規定したECデータベース指令の特徴と、その後の各国での国内法の整備状況,最近の訴訟例を紹介)
- 長塚 隆、 「データベースの法的保護 - ヨーロッパにおけるデータベースの新たな権利
sui generis をめぐる最近の動き」、情報管理、44(5),
322, 2001.
(特許戦争に対する関心の増加傾向はビジネス方法の特許および遺伝子関連特許で代表される情報技術分野の出願との相関関係が極めて大きい)
- 平川 美夏、松邑 勝治、黒田 雅子、 「ヒトゲノム情報とデータベースの利用
- ヒトゲノム情報統合データベースHOWDYの開発を通じて」、情報管理、44(5),
342, 2001.
(ヒトゲノム情報統合データベース HOWDY の概要)
- 久保田啓介「デジタル情報の消失に備え米国で対策が本格化」、日経サイエンス、2001(9),
102-104
(元米国国立公文書館プロジェクトリーダー Charles M. Dollar 氏に聞く)
- Gary Stix, 「特許範囲の拡大解釈に歯止め」、日経サイエンス、2001(8),
122 ("Staking
Claims: A License for Copycats?", Scientific
American, June, 2001.)
(米国の控訴審で特許の範囲を狭める判決が出た)
- 「ハイインパクト論文と研究評価の今後」、現代化学、2001(8),
36-37.
(ハイインパクト論文の検討)
- 村田 徳治「化学物質の自主管理制度 - PRTR 法の要点と問題点」、現代化学、2001(8),
63-67.
(環境汚染物質排出移動登録 (PRTR) 制度について)
- 長阪 匡介、近藤 隆、愛宕 隆治、前田 知子、飯島 邦男、間下 健太郎、
「物質・材料系データベースの現状と今後」、情報管理、44(4),
245-257, 2001.
(平成 12 年度実施の「物質・材料系のデータベースの整備・構築に関する調査」に基づき、高分子、金属、その他のデータベースの現状と今後)
- 佐々木宏子、「新・世界の医薬品集 (2)、ヨーロッパ - その 1」、薬学図書館、46(2),
107-128, 2001.
(イギリス、イタリア、オーストリア、オランダの医薬品集)
- 松田 真美、「医学中央雑誌インターネットサービスについて (3) 「Advanced
Mode」のご紹介など」、薬学図書館、46(2), 129-132, 2001.
(Advanced Mode と「Pre医中誌」)
- 松下 茂、「日本のドキュメントデリバリーサービス: 現状と課題」、薬学図書館、46(2),
133-138, 2001.
(海外の DDS サービス、JICST, JAPIO, IMIC などのサービスの紹介、著作権処理の問題点、)
- 上野 京子、「SciFinder Scholar」、薬学図書館、46(2),
156-159, 2001.
(SciFinder Scholar の解説)
- 大野 宏治、「MICROMEDEX Health Care Series」、薬学図書館、46(2),
160-164, 2001.
(中毒情報、医薬情報、救急医療、代替医療のデータベース)
- 梶 正憲、「医学・薬学予稿集全文データベースの概要」、薬学図書館、46(2),
165-168, 2001.
(約 200 の医学・薬学分野の学会予稿集の PDF)
牛島 裕、「近畿大学における Sicence Direct 利用の事例」、薬学図書館、46(2),
169-176, 2001.
(1999-2000 における利用状況統計)
- 船津 公人、 「知識の構造化のためのデータ真イニング - 情報の地図を作る」、化学と工業、54(5),
555-559, 2001.
(データのモデル化、候補の評価方法、候補のスクリーニング、などの手法と材料開発への応用について)
- 富岡 秀雄、 「欧文誌と図書館と - 学会誌の危機 (投稿)」、化学と工業、54(4),
496, 2001.
(商業誌の高騰、学会誌の危機について)
- 松田 和之、「情報検索の未来像 - 学術情報の生産流通過程の変革とデジタル・コンテンツ」、情報の科学と技術、51(5),
262-265, 2001.
(Web 検索、商用データベース、検索技術など)
- 松山 裕二、「電子ジャーナルと文献データベースの方向」、情報の科学と技術、51(5),
266-270, 2001.
(電子ジャーナルの歴史と展望)
- 深見 拓史、「電子出版から見た『これから』」、情報の科学と技術、51(5),
271-276, 2001.
(書籍を中心とした商業電子出版の現状と今後)
- 小山内 正明、「次世代のサイエンス・ダイレクト - 文献検索の新しい局面」、情報の科学と技術、51(5),
277-280, 2001.
(Science Direct の検索と Scirus の紹介)
- 長塚 隆、「データベース・ディストリビュータから見た『これから』 -
ジー・サーチの新規サービス」、情報の科学と技術、51(5),
281-284, 2001.
(G-Search と Dialog の統合日本語インタフェース InfoPro Station について)
- 福島 三喜子、「データベース・ディストリビュータから見た『これから』
- STN サービスの現状と今後の展開について」、情報の科学と技術、51(5),
285-287, 2001.
(STN Express, STN on the Web, ChemPort など)
- 設楽 真理子、「データベース・ディストリビュータから見た『これから』
- データベース・ディストリビュータ生き残りの道」、情報の科学と技術、51(5),
289-292, 2001.
(Ovid の例)
- 本間 文子、「PATOLIS 高分子関連複合語フリーキーワードの検討 - 高分子関連複合語フリーキーワードの信頼性評価」、情報の科学と技術、51(3),
167-173, 2001.
(高分子関連複合語フリーキーワードは汎用ポリマーで出現頻度の高い表記の場合にのみ有効である)
- ミッショー、ウィリアム H、 「XML 技術と学術コミュニケーション」、情報管理、44(3),
163-173, 2001.
(イリノイ大学における電子ジャーナルプロジェクトを中心に XML の利用について)
- 齋藤 絵理、小野寺 夏生、 「Web 上の学術情報資源におけるメタデータの利用」、情報管理、44(3),
174-183, 2001.
(Web 情報のメタデータを提供する Subject Gateway について)
- 高木 奈津子、加藤 秀樹、菊地 博道、 「JST の英文データベースとインターネットによる提供」、情報管理、44(3),
190-198, 2001.
(JICST-E ファイルの Web での無料提供 <http://j-east.tokyo.jst.go.jp>)
- 長田 孝治、田中 亮、西 啓志、鈴木 泰二、鎌田 栄一、高江 慎一、岩橋 香奈、剣持 和弘、
「化審法届出業務の電子化 - XML を用いた大容量報告書データの電子化とデータベース化について」、情報管理、44(2),
104-112, 2001.
(XML を用いた届け出電子化システム)
- 白木澤 佳子、小原 満穂、尾身 朝子、清水 卓彦、 「J-STAGE
における XML への取り組みについて」、情報管理、44(2),
113-124, 2001.
(電子ジャーナルシステム J-STAGE のデータベースに XML を使用するための開発)
- 李 錫浩、曺 順英、内田 尚子訳、 「韓国における大学の電子図書館と情報政策」、情報管理、44(2),
125-131, 2001.
(大学図書館のデジタル化、KERIS など)
- 長江 英夫、石田 文雄、 「東海豪雨による研究所の水害状況 - 特に研究資料および保管施設の被害状況と水害を想定した危機管理の今後のあるべき姿」、情報管理、44(2),
132-139, 2001.
(文書、写真、ビデオ、FD、CD-ROM などの被害状況)
- 倉田 敬子、 「学術情流通の新たな方向性 - 科学コミュニケーションと電子メディア」、情報知識学会誌、11(1),
2-10, 2001.
(電子雑誌、e-print アーカイブなど)
- 阿部 信一、「米国国立医学図書館と長期計画」、医学図書館、48(2),
162-173, 2001.
(NLM の 2000-2005 年長期計画について)
- 大瀧 礼二、「National Network of Libraries of Medicine (NN/LM) の
Outreach 活動」、医学図書館、48(2), 174-181,
2001.
(医学図書館のネットワーク活動について)
- 小澤 ゆかり、「NLM の Web ページ」、医学図書館、48(2),
182-186, 2001.
(PubMed, LOCATORplus, MEDLINEplus, NLM Gateway など)
- 城山 泰彦、「日本の論文をもっと海外に発信するためには: 日本の医学雑誌の
MEDLINE 収載状況分析を通して」、医学図書館、48(2),
187-197, 2001.
(和文誌では 97 誌中 35 誌、欧文誌では 48 誌中 28 誌が MEDLINE に収載されている)
- 澤田 こず恵、「『海外医薬品文献速報』におけるフリーキーワードと MeSH
の比較」、医学図書館、48(2), 213-217, 2001.
(国際医学情報センターが ProQuest を使用して作成している同サービスを PubMed
と比較)
- 野口 靖夫、「『情報』という言葉と遊ぶ」、学士会会報、(831), 139-143,
2001.
(「情報」という言葉の起源について)
- 殿崎 正明、「エルゼビア・サイエンス社の 2000 年 - 2001 年雑誌円建価格問題」、医学図書館、48(1),
93-94, 2001.
(図書館 3 団体のシンポジウム、および公正取引委員会への審査請求などの経過の解説)
- 相良 尚宏、「医中誌@InfoStream」、医学図書館、48(1),
115-116, 2001.
(日本電子計算 (株) 提供のサービスの紹介)
- 田中 秀明、 「Web of Sciece を用いた研究評価の試みと留意点」、情報管理、44(1),
2-7, 2001.
(工業技術院生命工学工業技術研究所、物質工学工業技術研究所、筑波大学化学、筑波大学応用生物研究、の論文数、被引用数の調査・解析)
- 白旗 保則、 「ディジタル・ドキュメンテーション - ドキュメントの電子化のためのシステムと手法」、情報管理、44(1),
8-16, 2001.
(総説)
- 池田 実、角井 恒、 「XML と情報共有」、情報管理、44(1),
17-27, 2001.
(XML の特徴、メタデータなど)
- 医薬情報ネット 21、 「インターネット無料情報源の有効活用について」、情報管理、44(1),
28-41, 2001.
(検索エンジン、無料電子ジャーナル、その他)
- 荒木 啓介、 「IPCクラソーラスの開発」、情報管理、44(1),
42-56, 2001.
(IPC を簡単に利用できるためのツール)
- 川口 義博、 「JOIS の STN Messenger によるサービスプロジェクトについて」、情報管理、44(1),
57-62, 2001.
(2003 年より実施される表記プロジェクトの概要)
- 本間 文子、「PATOLIS 高分子関連複合語フリーキーワードの検討 - 高分子関連複合語フリーキーワードの信頼性評価」、情報の科学と技術、51(3),
167-173, 2001.
(PLASDOC オンライン研究会関西グループによる、標記研究の報告)
- 丹 信全、山崎 むつみ、 「化学系雑誌の計量書誌的検討」、情報管理、43(12),
1059-1070, 2001.
(J. Catal., Anal. Chem., J. Polym. Sci. (Part A), の 3 誌について論文の投稿受付、採択、刊行の間の時間を調査し、また引用情報源のドキュメント・タイプ別、年代別の構成を調査した)
- 佐藤 弘行、松原 幸隆、東口 志穂、今井 敬子、内藤 衛亮、 「第 2
回東南アジア科学技術情報流通 (CO-EXIST-SEA) ワークショップ」、情報管理、43(12),
1105-1116, 2001.
(2000. 10 に JST がハノイで開催した標記ワークショップの報告)
- シュベンス, ウテ、 「ドイツ図書館におけるディジタル出版物の長期保存
(ディジタル・アーカイビング) について (インタビュー)」、情報管理、43(12),
1137-1142, 2001.
(オンライン系出版物については交渉中)
- 有住 玲子、「GMELIN Handbook 全書の紹介とその調べ方」、科学技術文献サービス、(120),
2-13, 2000.
(無機化合物と有機金属化合物の全書 GMELIN の解説)
- 名和 小太郎、大谷 和子、「情報フロンティアシリーズ
- IT ユーザの法律と倫理」、共立出版、180
pp., 2001.>
第 1 章 情報の法律
第 2 章 論点 - 法律で決まっていること、決まっていないこと
第 3 章 情報倫理をめぐって
- 朽津 耕三、「よい速報論文を迅速に発表するには」、現代化学、2001(2),
62-67.
(Chemical Physics Letters 編集委員の経験から)
- 久保 忠道、「検証 - MEDLINE Web Sites」、薬学図書館、46(1), 18-28,
2001.
(PubMed, Internet Grateful Med, Medscape, HealthGate, Infotrieve, Community
of Science, BioMedNet, Free MEDLINE (Knowledge Finder), Paper Chase, Free
MEDLINE/grips WeSearch, MD Consult, Dematel, MEDLINE (UKOLN), Physicaians'
Online, MedFetch (AMQ), DubMed などの比較)
- 松本佳代子、「薬学と EBM - リサーチライブラリアンへの期待」、薬学図書館、46(1),
29-34, 2001.
(Evidence-Based Medicine 情報について)
- 浅井泰博、「Evidence-Based Medicine と情報検索」、薬学図書館、46(1),
46-49, 2001.
(Evidence-Based Medicine のデータベース)
- 母良田 功、「日本薬学図書館協議会における Elsevier Science 社の購読雑誌」、薬学図書館、46(1),
52-54, 2001.
(日本薬学図書館協議会は Elsevier Science にとって 11 億 4000 万円の市場になっており、2001
年は円とギルダーの乖離により 6 億 8 千万円も払いすぎになっている)
- 松田 真美、「医学中央雑誌インターネットサービスについて (2) 医中誌
WEB 検索の実際」、薬学図書館、46(1), 55-60, 2001.
(検索例)
- 佐々木宏子、「新・世界の医薬品集 (1)、総論・北アメリカ」、薬学図書館、46(1),
61-84, 2001.
(AHFS Drug Information, American Drug Index, Drug Facts and Comparison,
PDR, Merck Index、など)
- 有賀 康裕、新井 大樹、 「US クラス 705 に関するパテントマップ解析」、情報管理、43(11),
965-975, 2001.
(ビジネスモデル特許の解析)
- 渡辺 和代、 「Dublin Core Metadata の紹介」、情報管理、43(11),
976-988, 2001.
(詳細な説明)
- ベントソン、ベティ G、 「ネットワーク世界における学術研究図書館の現実と選択」、情報管理、43(10),
895-908, 2001.
(米国の研究図書館の現状)
- 志村 和樹、吉田 健司、中島 律子、渡辺 昭次、牧 幸浩、大崎 健次、
「JST における結晶構造データベースの構築 - データ入力支援システムと XML
の活用」、情報管理、43(10),
917-925, 2001.
(XEdit を使ったデータ入力)
- 磯谷 峰夫、 「京都大学電子図書館システムの現状」、情報管理、43(10),
926-932, 2001.
(電子図書館の発信と利用状況)
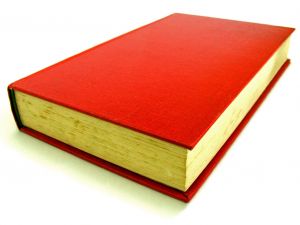 日本図書館情報学会研究委員会編.
「電子図書館 - デジタル情報の流通と図書館の未来」. 勉誠出版. 2001, 204p.
日本図書館情報学会研究委員会編.
「電子図書館 - デジタル情報の流通と図書館の未来」. 勉誠出版. 2001, 204p.
- デジタル時代の情報流通
- 情報流通の変化と電子図書館構築への取組み
- 電子図書館実現への課題
-1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, Latest