化学情報、薬学情報、データベースに関する文献
2003 年 (国内)
-1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, Latest
- 花井 荘輔、「はじめの一歩!化学物質のリスクアセスメント
図と事例で理解を広げよう」, 2003, 丸善, 3,675 円.
(化学物質のさまざまなリスクを評価する手法について解説)
- ヴィクトリア・ロバートソン, 加藤 信哉 訳, 「電子ジャーナルが大学図書館に及ぼす影響:
雑誌部門、収書部門および相互貸借部門の役割と機能の変化」, オンライン検索,
2003, 24(3/4), 155-163.
(ILL と雑誌部門への影響が大きい)(Interlending & Document Supply, 2003,
31(3), 174-179. より翻訳)
- 殿崎 正明, 「エルゼビア問題と学術情報流通における司書の役割」, オンライン検索,
2003, 24(1/2), 1-2.
(「買わない」、「投稿しない」、「査読者・編集者にならない」の 3 ない運動を提唱)
- 松田 真美, 「医中誌 Web (Ver.3) の機能と特徴」, オンライン検索, 2003,
24(1/2), 35-45.
(Ver. 3 の紹介)
- 廣松 康一、「化学物質安全性データベース・化学物質特性予測システム」,
CICSJ
Bulletin, 2003, 21(4), 80-81.
((財) 化学物質評価研究機構で提供しているデータベースと予測システム)
- 中島 眞人、「医薬品機構における医薬品情報提供」, CICSJ
Bulletin, 2003, 21(4), 84-87.
(医薬品機構 (現独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
の医薬品情報提供システム)
- 中山 伸一、「図書館情報学専門学群学生に対する情報化学教育」, CICSJ
Bulletin, 2003, 21(3), 70-71.
(筑波大学の経験)
- 細矢 治夫、「量子化学文献データベース (QCLDB) 四半世紀目の衣替え」,
CICSJ
Bulletin, 2003, 21(1), 2-6.
(QCLDB の歴史と現状)
- 白石 寛明、岡 敬一、「化学物質データベース (WebKis-Plus) について」,
CICSJ
Bulletin, 2003, 21(1), 7-10.
(開発の経緯と維持管理における問題点)
- 倉田 香織、濱田 真向、土橋 朗、「3 次元医薬品構造データベース (Three
Dimentional structure Database (3DPSD))
を作る」, CICSJ
Bulletin, 2003, 21(1), 11-15.
(1254 種の医薬品、JChem で構造検索)
- 早水 紀久子、「スペクトルデータベースの現状について」, CICSJ
Bulletin, 2003, 21(1), 16-19.
(SpecInfor, CSEARCH, NIST, KnowItAll, ACD, 1HNMRDB)
- 伊藤 暢聡、楠木 正巳、中村 春木、「タンパク質立体構造データベースの高度化:
PDBj」, CICSJ
Bulletin, 2003, 21(1), 20-23.
(PDBj-ML の開発、二次データベースの開発)
- 舘 田鶴子、「自然科学系電子リソース契約の現状と運用上の課題」, MediaNet,
2003, (10), 12-13.
(慶応義塾大学における電子ジャーナル購読契約)
- 市古 みどり、「データベース・電子ジャーナル契約における課題: Web of
Science の契約更改交渉から学んだこと」, MediaNet, 2003, (10), 14-15.
(慶応義塾大学における接続トラブルの補償の要求)
- 加藤 好郎、「電子媒体に特化した文部科学省の補助金獲得について」, MediaNet,
2003, (10), 16.
(私立大学情報教育協会の活動)
- 加藤 信哉、「電子ジャーナルの出版・契約・利用統計」,
カレントアウェアネス,
2003, (278), CA1512.
(米国研究図書館協会 (ARL) の統計など)
- 矢野 直明、「情報社会におけるディスコミュニケーション体系について」、情報処理,
2003, 44(12), 1284-1285.
(顧客からのコミュニケーションを拒否するシステムが広がっている)
- 黒澤 節男、「図書館と著作権」、医学図書館、50(4),
325-330, 2003.
(著作権制度のあらまし、電子的資料と著作権)
- 藤田 節子、「著作権における仲介者としての新たな図書館の役割」、医学図書館、50(4),
331-336, 2003.
(図書館が著作権処理の仲介をすることが求められている)
- 加藤 均、「複写サービスを提供する側から見た著作権」、医学図書館、50(4),337-340
, 2003.
(国際医学情報センターの経験)
- 児玉 閲、「非営利団体が目指す電子ジャーナルのインパクト」、医学図書館、50(4),
353-360, 2003.
(Highwire Press, BioMed Central, SPARC など)
- 高林 哲、「検索技術論」、NIKKEI
BYTE、(248), 101-108, 2003.
(検索システム Namazu の開発者の話)
- 小川 裕子、「審査官による先行技術文献調査と無料で使えるユニークなデータベース活用法」、情報管理、46(9),
575-586, 2003.
(三極特許庁提供のデータベース)
- 村田 一彦、「電子メールアーカイブおよび検索機能」、情報管理、46(9),
594-602, 2003.
(ビジネスリスク低減のための組織におけるアーカイブ)
- 近道 暁郎、「企業活動と知的財産制度 第 7 回: 植物新品種登録制度の現状と課題」、情報管理、46(9),
608-618, 2003.
(植物新品種登録制度の概要)
- 名和 小太郎、「セキュリティ文化 (下)」、情報管理、46(9),
624-625, 2003.
(OECD の「プライバシー保護と個人データの越境流通に関するガイドライン」)
- 竹中 繁織、 「私と特許 - 研究から特許出願へ」、化学と工業、56(12),
1309-1311, 2003.
(九州大学)
- 野浪 享、 「私と特許 - アパタイト被覆二酸化チタン光触媒の開発」、化学と工業、56(12),
1312-1313, 2003.
(産業技術総合研究所)
- 大石 正芳、吉田 慶志、 「大学と特許 - TLO から見た特許戦略」、化学と工業、56(12),
1314-1316, 2003.
(大阪 TLO)
- 鴨志田 洋一、 「企業から見た特許戦略」、化学と工業、56(12),
1317-1320, 2003.
(JSR)
- 吉井 一男、 「明細書を書くための One Point 集」、化学と工業、56(12),
1321-1324, 2003.
(明細書の書き方)
- 保田 明夫、「テキストマイニングの技術と適用性」、薬学図書館、48(4),
247-252, 2003.
(テキストマイニングの概要)
- 小林 義行、中江 裕樹、「日立製作所が提案する医薬向けテキストマイニング」、薬学図書館、48(4),
253-257, 2003.
(名称辞書、情報抽出技術、統計的自然言語処理からなる)
- 山田 訓、「情報検索システム IV Map」、薬学図書館、48(4),
253-257, 2003.
(三菱電機のシステム)
- 上野 京子、「ChemPort」、薬学図書館、48(4),
264-271, 2003.
(ChemPort の機能)
- 本多 玄、「東京大学における SciFinder Scholar/ChemPort と電子ジャーナルの連携事例」、薬学図書館、48(4),
272-276, 2003.
(ChemPort から電子ジャーナルへのリンク)
- 伊藤 勝、「学術論文販売とパーミッションサービス - 株式会社ナレッジワイヤ」、薬学図書館、48(4),
277-281, 2003.
(論文販売の DocumentWire とパーミッションサービスの RightsWire, ReprintWire)
- 山田 奬.「Medical Online」、薬学図書館.
2003, 48(4), 282-286.
()
- 杉本 重雄、「新たな電子図書館像の構築に向けて」、情報の科学と技術、53(12),
574-580, 2003.
(電子図書館とメタデータ)
- 酒井 美佳子、「韓国の特許データベース『KIPRIS』」、情報の科学と技術、53(12),
609-614, 2003.
(日本 EPI 協議会の評価報告 )
- 小林 晴子、坪内 政義、「電子ジャーナルが図書館サービスに与える影響」、医学図書館、50(3),
218-225, 2003.
(愛知医科大学医学情報センターの経験、利用アンケート)
- 菊地 博達、「Chemical Abstracts から電子ジャーナルへ: 私の文献検索の道」、医学図書館、50(3),
226-29, 2003.
(Current Contents, Chemical Abstracts, Index Medicus, MEDLINE, CDm PubMed)
- 藤田 昌久、「電子ジャーナルを利用して」、医学図書館、50(3),
230-231, 2003.
(電子ジャーナルの便利さ)
- 「医学図書館」編集委員会、「『電子ジャーナル』出版社アンケート調査結果報告」、医学図書館、50(3),
232-251, 2003.
(今後の契約携帯、コンソーシアムの考え方、アクセス障害、パッケージの組み替え問題、価格政策、FTE、個人契約と機関契約、値上げの理由、アーカイブ、アーカイブの安全性、契約中止後のアクセス権、文献複写、無料ジャーナル、大量ダウンロード、Pay
per View、PubMed LinkOut、パスワード認証、インタフェースの統一、要望)
- 殿崎 正明、「高騰する学術情報 - 洋雑誌・電子ジャーナル・データベース」、専門図書館、(201),
31-41, 2003.
(医学図書館協会のコンソーシアムの経験)
- 「実験化学講座
第5版 1 基礎編 1 実験・情報の基礎 1」、丸善,
2003 (3.2 「化学情報の受信 - インターネットの利用」 (49 pages) )
(SciFinder などの使い方)
- 杉本 重雄、「XML とメタデータ - メタデータの基本概念」、情報知識学会誌、13(4),
16-23, 2003.
(Dublin Core その他)
- マクネイリー, デイヴィッド, ミューレン, アレクサンダー:共著, 高木
和子:訳、「ヨーロッパ製薬業界における情報管理への挑戦」、情報管理、46(8),
518-529, 2003.
(P-D-R の歴史と活動)
- 高橋 雄一郎、「企業活動と知的財産制度 第 6 回: 回路配置利用権登録制度の現状と課題」、情報管理、46(8),
499-508, 2003.
(回路配置利用権登録制度の概要)
- 植松 利晃、「J-STAGE の現状と J-STAGE2 の開発」、情報管理、46(8),
536-545, 2003.
(横断検索、早期公開、バーチャルジャーナル、全文 HTML 化)
- 名和 小太郎、「セキュリティ文化 (上)」、情報管理、46(8),
552-553, 2003.
(OECD の「プライバシー保護と個人データの越境流通に関するガイドライン」と「情報システム・セキュリティ・ガイドライン)
- 福島 俊一、「Web サーチエンジンの基本技術と最新動向 (下) 基本技術」、情報管理、46(7),
436-445, 2003.
(リンク解析の改良・高度化、サーチエンジンスパム)
- 名和 小太郎、「2つの文化,あるいは S1 文化と S2 文化」、情報管理、46(8),
552-553, 2003.
(セキュリティの文化とサイエンス・コミュニティの文化)
- Gary Stix、「個人の創意は大切だけど...」、日経サイエンス、2003(12),
119-121.
(奇妙な特許の実例)("Staking Claims: Kick Me, Myself and I ",
Scientific American,
2003(10), 42.)
- Gary Stix、「続・えっ,これが特許なの?」、日経サイエンス、2003(10),
.
(奇妙な特許の実例)("Staking Claims: What a Little Limeade Can Do",
Scientific American,
2003(8), 32.)
- Gary Stix、「えっ,これが特許なの?」、日経サイエンス、2003(9),
.
(奇妙な特許の実例)("Staking Claims: Staking Claims: You Can Patent
That? ", Scientific
American, 2003(7), 32.)
- 佐藤 寛子、中田 忠、「化学研究における実践的活用を指向した化学反応データベースの検証」、Journal
of Computer Chemistry Japan、2(3), 87-93, 2003
(ChemInform の 60 万件の化学反応データの信頼性の検証.)
- 中田 彰生、「図書館における新聞記事電子化の著作権問題」、情報の科学と技術、53(11),
557-561, 2003.
(クリッピングサービス、デジタル化などの著作権問題)
- 山田 清明、「企業活動と知的財産制度 第 5 回: 知的財産権侵害物品の水際取締りの現状と課題」、情報管理、46(7),
427-435, 2003.
(関税定率法、輸入差止申立制度など)
- 福島 俊一、「Web サーチエンジンの基本技術と最新動向 (下) 最新技術」、情報管理、46(7),
436-445, 2003.
(リンク解析、サーチエンジン最適化など)
- 名和 小太郎、「2つの文化,あるいは S1 文化と S2 文化」、情報管理、46(7),
475-477, 2003.
(セキュリティの文化とサイエンス・コミュニティの文化)
- 石岡 克俊、「企業活動と知的財産制度 第 4 回: 技術革新と国際的調和の中の著作権法」、情報管理、46(6),
354-362, 2003.
(著作権法の歴史)
- 福島 俊一、「Web サーチエンジンの基本技術と最新動向 (上) 基本技術」、情報管理、46(6),
363-372, 2003.
(索引と検索、ランキング)
- 林 和弘、太田 太田暉人、小川 桂一郎、「日本化学会の電子ジャーナル化:
J-STAGE 利用の現状と課題」、情報管理、46(6),
373-382, 2003.
(電子ジャーナル化の概要、電子ジャーナル化の成果、課題の解決J-STAGE と学会、など)
- 菊池 俊一、「地球規模生物多様性情報機構 (GBIF) およびその国内対応」、情報管理、46(6),
389-393, 2003.
(国際協力による地球規模の分散データベース)
- 名和 小太郎、「一世紀前のニューメディア論 (下)」、情報管理、46(6),
403-404, 2003.
(映画の著作権の歴史)
- 箕輪 成男、「学術出版システムの根底にあるもの」、情報の科学と技術、53(9),
417-422, 2003.
(学術出版の両義性、著作権、流通システム、英文出版、社会コストなど)
- 鈴木 哲也、「大学出版部は存在意義を示せるか - 京都大学学術出版会の取り組みから」、情報の科学と技術、53(9),
423-428, 2003.
(出版不況の中での大学出版部の課題)
- 安達 淳、根岸 正光、土屋 俊、小西 和信、大場 高志、奥村 小百合、「SPARC/JAPAN
にみる学術情報の発信と大学図書館」、情報の科学と技術、53(9),
429-434, 2003.
(日本の学術論文の海外流出、学術雑誌電子化と大学図書館の対応、日本の学術雑誌電子ジャーナル化の現状、SPARC/JAPAN
の現状)
- 長塚 隆、「海外における電子出版の最新動向 - 学術分野の電子ブックを中心に」、情報の科学と技術、53(9),435-440,
2003.
(電子ブックについて)
- 林 和弘、門條 司、「日本化学会での学術情報発信と流通」、情報の科学と技術、53(9),441-447,
2003.
(日本化学会の J-STAGE を利用した学術雑誌の電子ジャーナル化の経緯、電子投稿)
- 佐々木 宏子、「新・世界の医薬品集 (6)、豪州・中南米・その他」、薬学図書館、48(3),
192-213, 2003.
(オーストラリア、中米・ドミニカ共和国、ブラジル、ペルー、メキシコ、イスラエル、ロシア連邦、南アフリカ共和国の医薬品集)
- 山本 佐知子、「inside web における電子的なドキュメントデリバリーについて」、薬学図書館、48(3),
224-227, 2003.
(The Britsh Library の inside web からのドキュメントデリバリーと EDD、Adobe
Acrobat eBook Reader について)
- 工藤 莞司、「企業活動と知的財産制度: 第 3 回: 商標登録制度の現状と課題について
- 不使用登録商標対策と商標の使用を巡る諸問題」、情報管理、46(5),
284-291, 2003.
(不使用登録商標がたまっている)
- 中田 吉郎、上林 正巳、神沼 二眞、「J-STAGE を利用した論文誌の刊行:
学際領域の論文誌のインターネットによる刊行」、情報管理、46(5),
303-310, 2003.
(CBI Journal の刊行の経験)
- 松村 多美子解説、カレン・ハンター、エルゼビア・ジャパン訳、「"アーカイブは『隠れ家』であってはならない":
エルゼビアにおけるデジタル・アーカイビング」、情報管理、46(5),
319-323, 2003.
(オランダ国立図書館との共同プロジェクト)
- 名和 小太郎、「一世紀前のニューメディア論 (上)」、情報管理、46(5),
329-330, 2003.
(発掘された古代遺物の所有権について)
- 網本 淳子、「医学・医薬品情報の探し方」、情報の科学と技術、53(8),
378-384, 2003.
(薬効、規制、市場、特許、学術文献、EBM、医学用語、学会情報、研究者・専門医、化合物辞書)
- 木内 貴弘、「UMIN による学会からの医学・医薬品情報の収集と提供」、情報の科学と技術、53(8),
385-390, 2003.
(AC-学会情報、ELBIS-文献情報、INDICE-臨床試験・疫学研究データ、OASIS-学会会員向け情報)
- 中島 眞人、「医薬品機構からの情報発信」、情報の科学と技術、53(8),
391-395, 2003.
(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の「医薬品情報提供システム」、添付文書、副作用が疑われる症例、各種安全性、新薬の承認、医薬品等の回収)
- 藤田 道男、「医薬品産業情報速報紙i『日刊薬業』」、情報の科学と技術、53(8),
396-400, 2003.
(『日刊薬業』の取材、執筆、制作)
- 山本 聡一郎、「医薬品開発情報データベース『明日の新薬』」、情報の科学と技術、53(8),
401-405, 2003.
(『明日の新薬』の情報収集)
- 田隅 三生、朽津 耕三、細矢 治夫、早水 紀久子、田辺 和俊、森岡 義幸、坂本 章、佐藤 寿邦、廣田 勇二、「化学データベース」、情報知識学会誌、13(3),
58-72, 2003.
(自由多原子分子の幾何学的構造データ、量子化学文献データベース、NMR スペクトルデータベース、赤外ラマンスペクトルデータベース、赤外ラマン文献データベース、電気化学データベース、ケンブリッジ結晶構造データベース、無機結晶構造データベース、金属結晶構造データベース、蛋白質分子構造データベース、CAplus、Registyr、CASREACT、Beilstein)
- 清貞 智会、「高度情報社会におけるサイエンス・コミュニケーション」、情報管理、46(4),
213-217, 2003.
(日本の研究の論文発表数と注目度)
- 鈴木 利之、「企業活動と知的財産制度: 第 2 回: 実用新案制度の現状」、情報管理、46(4),
224-232, 2003.
(実用新案制度は 1994 年に無審査になってから出願が激減した)
- 名和 小太郎、「『死海文書』の所有権 (下)」、情報管理、46(4),
259-260, 2003.
(発掘された古代遺物の所有権について)
- 青山 紘一、「企業活動と知的財産制度: 第 1 回: 特許法制度の現状と課題」、情報管理、46(3),
154-163, 2003.
(特許制度の基本)
- 中西 博, 大塚 加奈子、「企業における電子図書館システムの構築と今後の展開」、情報管理、46(3),
164-172, 2003.
(東芝研究開発センター図書館の実例)
- 名和 小太郎、「『死海文書』の所有権 (上)」、情報管理、46(3),
188-189, 2003.
(発掘された古代遺物の所有権について)
- 細野 公男、「デジタルコレクションの構築とその課題」、情報の科学と技術、53(7),
330-336, 2003.
(デジタル化を進める際の問題点)
- 清水 宏一、治田 嘉明、「デジタルアーカイブの現状と美術品・資料の電子化」、情報の科学と技術、53(7),
337-342, 2003.
(美術館・博物館・図書館における収蔵物のデジタル化)
- 金澤 勇二、「紙文書のデジタル化と情報の寿命」、情報の科学と技術、53(7),
343-348, 2003.
(マイクロフィルムのデジタル化)
- 高橋 仁一、「デジタルアーカイブの保存・利用における諸問題」、情報の科学と技術、53(7),
349-354, 2003.
(大日本印刷がフランス国立美術館連合 (RMN) と共同で進めている美術品のアーカイブ・プロジェクトについて)
- 小野 博、「デジタル画像データの応用・その可能性」、情報の科学と技術、53(7),
355-360, 2003.
(東北大学付属図書館所蔵の資料のデジタル化、原寸復元、デジタル修復、屏風作成など)
- 西沢 康、「『明治・大正・昭和の読売新聞 CD-ROM』について」、情報の科学と技術、53(7),
361-366, 2003.
(マイクロフィルムのデジタル化、索引データ作成、検索上の留意点など)
- 時実 象一、「化学物質の同定とそのツール」、化学経済、2003(11),
92-98.
(CAS 登録番号と検索ツール STN Easy, JOIS Easy)
- 中地 重晴、「インターネットによる化学物質提供 - NGO の取り組み」、化学経済、2003(10),
99-104.
(「有害化学物質削減ネットワーク (T ウォッチ)」について)
- 増田 陽子、「化学物質の総合的な情報提供について」、化学経済、2003(9),
94-100.
(独立行政法人製品評価技術基盤機構の「化学物質総合情報提供システム」について)
- 相澤 寛史、「化学物質アドバイザーのパイロット事業について」、化学経済、2003(8),
84-88.
(環境省の新しい資格)
- 大野 博、「化学物質を中心とした安全衛生情報の提供」、化学経済、2003(7),
89-94.
(中央労働災害防止協会の提供するデータベース、労働災害事例、死亡災害事例、安全衛生法関係化学物質、変異源性化学物質、モデル
MSDS、など)
- 池田 良弘、「化学物質とインターネット情報 第 4 回: 日化協による化学品安全性情報提供」、化学経済、2003(6),
101-107.
(「化学製品情報データベース」について)
- 井口 忠男、「化学物質とインターネット情報 第 3 回: 化学企業の化学物質管理と IT
- 三菱化学の取り組み」、化学経済、2003(5),
89-97.
(「環境・安全 DB」について)
- 関澤 純、「化学物質とインターネット情報 第 2 回: IT 化に伴う化学物質情報検索の変容」、化学経済、2003(4),
94-99.
(Web で検索できる化学物質情報)
- 岡 敬一、「化学物質とインターネット情報 第 1 回:インターネットによる化学物質情報提供
- 地方自治体の取組み」、化学経済、2003(3),
70-77.
(神奈川県環境科学センターの「化学物質安全情報提供システム (kis-net)」について)
- 千原 秀昭、深田 良治、長塚 隆、三浦 勲、長縄 友子、松村 多美子、「座談会:
科学技術情報電子化の動向」、ペトロテック、26(6),
2-14, 2003.
(デジタル化を進める際の問題点)
- 池田 正、「電子著作権管理」、情報管理、46(2),
79-89, 2003.
(コピープロテクション技術,暗号化技術,電子透かし技術および電子著作権管理システム)
- 中村 達生、「JICST ファイル・特許 DB を用いた動向分析 - データマイニング手法を用いた技術連関分析」、情報管理、46(2),
97-106, 2003.
(人工知能分野,液晶分野,バイオテクノロジー分野の論文について,特許文献との技術連関分析を行った)
- 辻丸 光一郎、「医療行為と特許 (下)」、情報管理、46(2),
107-112, 2003.
(日本の特許制度は,医薬品や医療機器の特許は認めるものの,医師が行う医療行為そのものを特許の対象としない)
- 山田 奬、「著作権シンドローム」、情報管理、46(2),
120-122, 2003.
(学術著作権について、図書館の貸し出しについて)
- 名和 小太郎、「アボリジニー作品の著作権」、情報管理、46(2),
123-124, 2003.
(伝統的知識は著作権になじむか)
- 中西 陽子、「複数のデータベースにおける抗菌物質研究に関する文献の索引語分析」、情報管理、46(1),
1-8, 2003.
(MEDLINE,EMBASE,BIOSIS の大腸菌の抗菌物質研究に関する文献の索引語分析)
- 辻丸 光一郎、「医療行為と特許 (上)」、情報管理、46(1),
17-24, 2003.
(日本の特許制度は,医薬品や医療機器の特許は認めるものの,医師が行う医療行為そのものを特許の対象としない)
- 長塚 隆、「情報商品のアグリゲーションサービス - Web時代におけるデータベースサービスの新たな動向」、情報管理、46(1),
34-41, 2003.
(「比較アグリゲーション」,「連携アグリゲーション」,「イントラアグリゲーション」および「インターアグリゲーション」について解説)
- 名和 小太郎、「リバース・エンジニアリング」、情報管理、46(1),
51-52, 2003.
(DVD の複製禁止を破る DeCSS)
- 山本 晧二. 「Server Side Script を用いた医療情報学会論文投稿査読システムの構築と評価」.
医療情報学.
2003, 23(2), 127-136.
(利用者ごと (著者,管理者,編集委員,査読者) に 4 つのサブシステムで構成、シンプルな形でデザイン)
(大会発表)
- 大野 博教、「文献計量学から見た日本のノーベル賞受賞科学者達の研究業績の特徴」、学士会会報、(840),
115-121, 2003.
(利根川、白川、野依、小柴、田中各氏の文献の分析)
- Gary Stix、「電子アーカイブで科学界を結束」、日経サイエンス、2003(7),
92-93.
(Paul Ginsparg の arXiv.org について)
- 滝 順一、「科研費の民間開放で大論争」、日経サイエンス、2003(7),
120-121.
(総合科学技術会議の意見書で科研費を民間にも開放することが提案された)
- 荻野 博、 「ドルトンの原子説 200 年」、現代化学、2003(6),
20-24.
(ドルトンと原子説)
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 11 章、雑誌目次
(TOC) とアラート (KMP)」、化学,
58 (10), 38-39, 2003.
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 10 章、雑誌目次
(TOC) とアラート (KMP)」、化学,
58 (10), 38-39, 2003.
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 9 章、物性データやスペクトルデータを探す」、化学,
58 (9), 42-43, 2003.
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 8 章、名前や分子式から化合物を探す」、化学,
58 (8), 44-45, 2003.
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 7 章、化学反応を検索する」、化学,
58 (7), 52-53, 2003.
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 6 章、部分化学構造の検索」、化学,
58 (6), 46-47, 2003.
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 5 章、化学構造を検索する」、化学,
58 (5), 48-49, 2003.
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 4 章、トピックを検索する」、化学,
58 (4), 48-49, 2003.
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 3 章、著者名で探す」、化学,
58 (3), 46-47, 2003.
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 2 章、SciFinder/SciFinder
Scholar のデータベース」、化学,
58 (2), 40-41, 2003.
- 時実 象一、「SciFinder 入門 - 化学情報に強くなる、第 1 章、SciFinder/SciFinder
Scholar ってなに?」、化学,
58 (1), 40-41, 2003.
- 浅井 将行、「効果的なコンソーシアムを考える - Wiley InterScience EAL
の場合」、薬学図書館、48(2), 77-80, 2003.
(昭和大学図書館の経験)
- 三隅 昌朗、「企業向け電子ジャーナル・コンソーシアムの現状と今後の課題について」、薬学図書館、48(2),
81-83, 2003.
(薬学図書館協議会のコンソーシアム)
- 黒木 文子、「5 種の電子ジャーナル・コンソーシアムに散会して - 東京薬科大学情報センターの事例報告」、薬学図書館、48(2),
84-86, 2003.
(ACS, Blackwell, EBSCO, LWW, Springer)
- 母良田 功、「日本薬学図書館協議会における電子ジャーナル・コンソーシアムの現状と課題」、薬学図書館、48(2),
87-91, 2003.
(雑誌問題検討委員会報告)
- デイビッド・ペンドルベリー、宮入 暢子抄訳、「研究評価のための ISI
社引用文席の展開 - その特性、解釈、誤用」、薬学図書館、48(2), 95-100, 2003.
(引用分析の 10 原則)
- 佐久間 せつ子、「医学中央雑誌データベースにおける EBM への取り組み」、薬学図書館、48(2),
107-110, 2003.
(「ランダム化比較試験 (RCT)」、「比較臨床試験 (CCT)」、「メタアナリシス
(MA)」、「比較研究 (CS)」の各タグを付与)
- 野田 利章、「医学薬学データベースの比較」、薬学図書館、48(2), 114-118,
2003.
(JMEDICINE, JAPICDOC, 医中誌、の 3 データベース)
- 高橋 昭治、「ScienceDirect の現状 - ポータルサイトとしての視点から」、薬学図書館、48(2),
132-136, 2003.
(電子ジャーナル、書誌データベース、レファレンスワークのリンクと統合)
- 鈴木 宏子、「千葉大学における ScienceDirect の利用」、薬学図書館、48(2),
139-143, 2003.
(導入の経緯、取り組み、得失、研究者の評価など)
- 青山 紘一、「研究成果の帰属と補償 (下) - 大学・公的研究帰還にける研究成果の帰属と管理」、情報管理、45(12),
845-857, 2003.
(現状と今後の動き)
- 平井 昭光、「マテリアル・トランスファー・アグリーメント」、情報管理、45(12),
858-867, 2003.
(研究材料の移転に関する契約について)
- 小川 裕子、「Web 上の有料、無料特許情報の案内と利用 第 3 回 - Web
上の検索システム「DB 航海士」と企業における特許情報の活用」、情報管理、45(12),
873-883, 2003.
(適切な特許データベースを見つけるツール)
- 名和 小太郎、「公有著作物の商用化」、情報管理、45(12),
889-890, 2003.
(レキシスを巡る裁判、など)
- 長尾 純子、佐藤 弘行、菊池 俊一、「研究開発支援総合ディレクトリ
(ReaD)」、情報管理、45(12),
891-894, 2003.
(研究活動情報の収集と提供)
- 藤井 敦、「Web 情報を用いた辞典検索サイトの構築」、情報の科学と技術、53(4),
201-204, 2003.
(Web 辞典検索システム CYCLONE)
- 佐藤 恵子、「JST リンクセンター」、情報の科学と技術、53(4),
211-215, 2003.
(J-STAGE と CrossRef, PubMed, ChemPort, JOIS などの間をリンクする
- 丸島 儀一、「産業競争力強化と知的財産」、情報管理、45(11),
745-752, 2003.
(米国のプロパテント政策、わが国の課題)
- 青山 紘一、「研究成果の帰属と補償 (上) - 職務発明の対価」、情報管理、45(11),
753-763, 2003.
(日立職務発明訴訟判決について)
- 原田 英二、渡辺 怜子、児嶋 紀子、水野 充、「電子ジャーナル一部売りの動向」、情報管理、45(11),
770-780, 2003.
(出版社、アグリゲータ、二次情報サービスなどの動き)
- 小川 裕子、「Web 上の有料、無料特許情報の案内と利用 第 2 回 - 各国特許庁
(中国、韓国、台湾、シンガポール、タイ) の活用と特許調査」、情報管理、45(11),
781-797, 2003.
(各国特許庁の Web サイトの紹介)
- 名和 小太郎、「アクセス・コントロール対学問の自由」、情報管理、45(11),
810-811, 2003.
(フェルテンの保護技術破壊に関する発表)
- 高木 和子、「激動の 2002 年図書館界 10 大ニュース」、情報管理、45(11),
812-816, 2003.
(愛国者法、インターネット検閲、著作権など)
- 青山 紘一、「『知的財産基本法』について」、情報管理、45(10),
673-678, 2003.
(目的、定義、基本理念、責務、基本的施策、戦略計画、戦略本部)
- 小川 裕子、「Web 上の有料、無料特許情報の案内と利用 第 1 回 - 各国特許庁
(米国、ヨーロッパ、イギリス、オランダ) の活用と特許調査」、情報管理、45(10),
679-689, 2003.
(各国特許庁の Web サイトの紹介)
- 野口 幸生、「デジタル・レファレンス・サービス - 動向と問題点」、情報管理、45(10),
696-706, 2003.
(インターネットを使ってのレファレンス・サービス)
- クリスティーナ・ウォルホーン、加藤 多恵子訳、「GetInfo - 科学技術資料のフルテキストを提供するドイツ発
Web サービス」、情報管理、45(10),
707-711, 2003.
(AIP, Karger Medical & Scientific, Kluwer Academic, German Oldenourg
などの電子ジャーナルと、ZBMED, SeB, INIST, BLDSC, RSC などからの文献複写)
- 名和 小太郎、「一時的複製は『複製』か」、情報管理、45(10),
717-719, 2003.
(CD やコンピュータ機器内にデータが一時的に滞留しているのは複製にあたるのか)
- 島田 昌、「J-STORE (研究成果展開総合データベース) について - 未公開特許の早期公開を中心として」、情報管理、45(10),
722-724, 2003.
(国などの研究成果を実用化に結びつけるための情報、特許紹介データベース、技術シーズデータベース、研究報告紹介データベース)
- 桐山 勉、長谷川 正好、川島 順、玉置 研一、吉田 郁夫、辻川 剛由、「インデクシングと検索の両視点から特許情報検索システムの今後の方向をさぐる
(考察と提案) - Fugmann (フーグマン) の自明な 5 原則ルールの示唆」、情報の科学と技術、53(3),
152-158, 2003.
(再現率と適合率の両方を高めるにはどうしたらよいか)
- 岡 紀子、仲 美津子、中北 美佐子、「製薬企業 Web サイトで見つける治験薬情報
- 治験薬データベースとの比較」、情報の科学と技術、53(2),
104-111, 2003.
(明日の新薬、Pioneer、Pharmaprojects, Cipsline, 薬事日報などと比較)
- 日本化学会学術情報部門、 「日本化学会論文誌の最近の動き」、化学と工業、56(2),
146-149, 2003.
(欧文誌、速報誌の電子化とその影響)
- 新保 斎、横山 茂之、隅蔵 康一、 「タンパク質立体構造は特許で保護されるか」、現代化学、2003(4),
61-68.
(構造座標特許、コンピュータープログラム発明、インシリコ・スクリーニング、など)
- 日和田 邦男、 「論点: 西村論文とそれに対する論点を読んで」、現代化学、2003(11),
70-71.
- 唐木田 健一、 「論点: 研究者の社会的責任」、現代化学、2003(9),
70-71.
- 西村 肇、 「論点: 栗原氏の主張を読んで」、現代化学、2003(8),
62-63.
- 栗原 清一、 「西村論文を読んで」、現代化学、2003(7),
62-63.
- 西村 肇、 「昭和電工鹿瀬工場は大量のメチル水銀を生成していた (下)」、現代化学、2003(4),
13-20.
(新潟水俣病事件について)
- 西村 肇、 「昭和電工鹿瀬工場は大量のメチル水銀を生成していた (上)」、現代化学、2003(3),
13-17.
(新潟水俣病事件について)
- 新保 斎、廣瀬 隆行、 「化学・バイオ研究者のための知的財産講座 11.
バイオ・化学分野の特許をめぐる話題 - エピローグ」、現代化学、2003(3),
40-42.
(遺伝子特許、ゲノム特許など)
- 新保 斎、廣瀬 隆行、 「化学・バイオ研究者のための知的財産講座 10.
強くて広い特許権を取得するために - 特許出願周辺の制度」、現代化学、2003(2),
39-40.
(特許出願の補正、分割出願、優先権主張出願、拒絶査定不服審判)
- 青山 紘一、「『知的財産法』について」、情報管理、45(10),
673-678, 2003.
(目的、知的財産の定義、基本理念、国などの責務、基本的施策、戦略計画、戦略本部)
- 服部 光泰、「法律文献の検索とレファレンス事例: 早稲田大学中央図書館レファレンスカウンターにおける事例を中心に」、医学図書館、50(1),
41-45, 2003.
(現行法令、新法令、条例、判例などの検索)
- 廣瀬 信己、「国立国会図書館におけるインターネット情報資源への取組み」、専門図書館、(197),
6-14, 2003.
(WARP は電子雑誌コレクション、ウェブサイト・コレクションからなる)
- 松下 茂、「切望される利用者の声を反映した著作権処理システムの確立」、薬学図書館、48(1),
3-6, 2003.
(最近の動きについて)
- 森 隆之、「文献複写問題における著作権管理のあり方と運用について」、薬学図書館、48(1),
9-13, 2003.
(テクノミック社の対応)
- 金子 康樹、「ISI Web of Knowledge について」、薬学図書館、48(1), 39-44,
2003.
(機能の解説)
- 辻井 喜美代、「京都大学における ISI Web of Knowledge の導入と評価」、薬学図書館、48(1),
45-49, 2003.
(導入の経緯と研究者の評価)
- 新井 喜美雄、「特許情報分析とパテントマップ」、情報の科学と技術、53(1),
16-21, 2003.
(ランキングマップ、時系列マップ、マトリクスマップ、その他の定量マップ、要旨マップ)
- 青木 仕、「医学情報における情報の解析 - 新しい情報環境の確立を目指して」、情報の科学と技術、53(1),
34-41, 2003.
(ビブリオメトリックス、ステップ・マップ、など)
- 岡本 拓司、 「戦前期の日本の化学とノーベル賞 - ノーベル賞選考資料から」、現代化学、2003
(1), 61-64.
(秦 佐八郎、鈴木梅太郎、など)
- 新保 斎、廣瀬 隆行、 「化学・バイオ研究者のための知的財産講座 9.
研究者と特許 - 田中耕一氏のノーベル賞受賞と特許」、現代化学、2003
(1), 66-69.
(田中氏の特許の説明と特許出願の重要性)
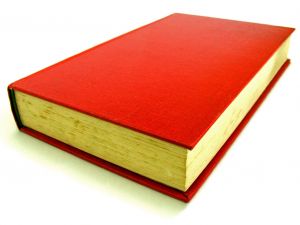 土屋 俊、安達 淳、高野 明彦、坂上 光明、増田 豊、「電子ジャーナルで図書館が変わる」、丸善、2003,
104 pp
土屋 俊、安達 淳、高野 明彦、坂上 光明、増田 豊、「電子ジャーナルで図書館が変わる」、丸善、2003,
104 pp
- 電子ジャーナルと大学図書館
- 学術雑誌の電子化
- 電子ジャーナル利用技術の研究動向
- 電子ジャーナル導入の実際
- 電子出版における海外の動向
-1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, Latest